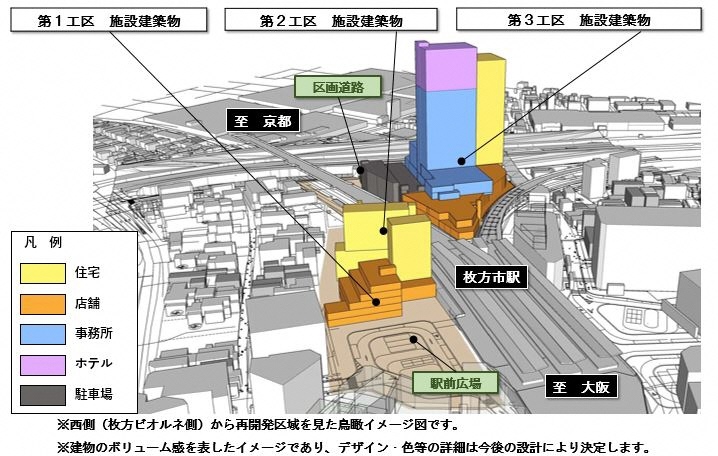仕事が消える瞬間は、いつも静かだ
『母をたずねて三千里』第1話で描かれる、マルコの仕事喪失の場面を、私はときどき思い出す。ワイン瓶を洗うという、家計を支える大切な仕事が、産業革命によって機械に置き換えられる。
そこに悪者はいない。努力不足でもない。
ただ、社会の仕組みが変わっただけである。
この「静かに仕事が消える感じ」は、いま私たちが直面しているAI革命と、驚くほど似ていると感じる。
AIは行政の現場にも入り始めている
AIはすでに、自治体の現場に入り込んでいる。
文書作成、議事録、問い合わせ対応、制度照会、データ整理。
これまで人が時間をかけて担ってきた業務が、驚くほど簡単に自動化されつつある。
これは「効率化」という言葉で語られることが多い。しかし、その裏側で起きているのは、行政の現場から「仕事」が少しずつ剥ぎ取られていくプロセスである。
問題は、人がいらなくなることではない。
人が担ってきた役割の意味が、曖昧になっていくことである。
公務員の仕事は、本当に守られているのか
自治体職員は、社会の中で最も「安定した仕事」の象徴のように語られる。
確かに、雇用という意味ではそうかもしれない。
しかし、AI革命が揺さぶるのは雇用そのものよりも、「なぜその人がそこにいるのか」という理由である。
書類を正確に作ること。
ルールを解釈し、前例に沿って処理すること。
これらは長らく自治の現場を支えてきたが、AIはそこを正面から代替してくる。
残るのは、責任だけかもしれない。
判断のプロセスはAIが提示し、人は承認印を押す存在になる。
そのとき、自治とは本当に「人が担っている」と言えるのだろうか。
奪われるのは「仕事」ではなく「関係性」
ここで重要なのは、AIが奪うのは仕事そのものではなく、
「人と人のあいだにあった関係性」だという点である。
窓口での雑談。現場での微妙な空気。
住民の言葉にならない違和感。
そうしたものは、効率の名のもとに、長らく「無駄」とされてきた。
しかし、それこそが行政の核心だったのではないか。
マルコが失ったのも、単なる労働時間ではない。
家族を支えているという実感であり、社会の中での役割である。
行政は「制度」ではなく「行為」である
AI時代において、行政の機能を制度として守ろうとするだけでは足りない。
行政とは、本来「誰かが誰かの声を受け止める行為」そのものだったはずである。
行政か住民か、という二項対立も、もはや古い。
これから問われるのは、どこに判断があり、誰が責任を引き受け、誰と一緒に考えるのか、という関係のデザインである。
AIによって事務が軽くなるなら、その余白をどこに使うのか。
その問いに答えられない自治体は、空洞化していくだろう。
希望がないわけではない。
すでに各地で、小さな自治の再編は始まっている。
住民と職員が肩書きを外して話す場。
計画よりも対話を重視するまちづくり。
制度の外にある声を拾い上げる実践。
これらはAIには代替できない。
なぜなら、それは正解を出す行為ではなく、関係を編み直す行為だからである。
マルコの物語を、予告編で終わらせないために
マルコは、仕事を失ったあと、母を探す旅に出る。
だが私たちは、旅に出る前に考えることができる。
AI革命は、すでに始まっているからだ。
自治に関わるすべての人にとって、「自分の仕事は何か」を問い直す時代である。それは、奪われる恐怖から始まる問いかもしれない。しかしその先には、自治をもう一度、人の手に取り戻す可能性がある。
このまちは、誰のものなのか。
その問いを、AIに委ねずにいられるかどうか。
いま、その分岐点に私たちは立っている。
<山口 達也>