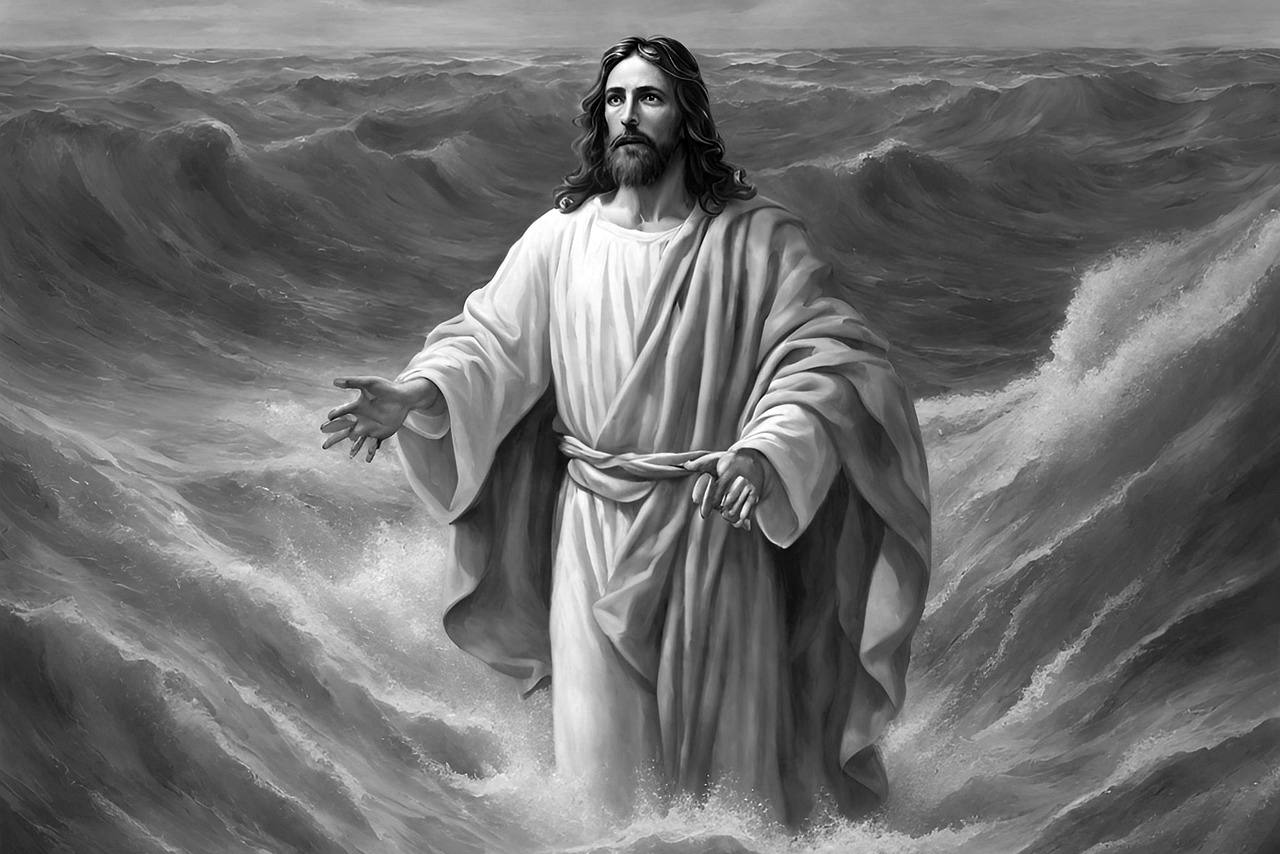—都構想の影に沈む10年の停滞
大阪市は、この10年あまり、大阪市を廃止して特別区を制定するいわゆる「都構想(以後都構想と称す)」をめぐる「なるか、ならないか」の議論に明け暮れてきた。
1回目に引き続き、2回目の理不尽な住民投票でその結果も出たのであるが、未だ副首都構想の影には3回目の住民投票が見え隠れする。
その結果、「どんな大阪を目指すのか」「どう暮らしを支えるのか」という大阪の都市としてのグランドデザインを描く力を失ってしまった。
制度論に時間を奪われた代償は、行政の機能低下や都市競争力の喪失として、今や街のあちこちに表れつつある。
10年の「制度迷走」が奪った実行力
都構想の是非を問う住民投票は2015年と2020年の2度にわたって行われた。いずれも僅差で否決されたが、問題はその結果ではなく、その議論の長期化にある。
市役所も府庁も「将来の制度が変わるかもしれない」という前提で、思い切った長期計画を打ち出せないまま、現在に至る。
都市開発、インフラ整備、行政改革のどれもが「仮設状態」のまま進められず、予算と人員が都構想関連の検討や説明業務に費やされている。
その間、建設された公共施設は、2016年の城東区役所複合施設、2025年の港区民ホールの複合施設の2棟ほど。大阪も夢洲の万博やIR計画に動いてはいるが、いずれも府主導であり、市としての都市像は不明瞭である。開発の是非はともかく、大阪市は「構想はあっても意思がない都市」へと変質してしまった。


都市基盤の更新遅れと“後手のまちづくり”
市街地の老朽インフラ、再整備を要する区役所庁舎、災害対応力の弱い公共施設群。これらは10年以上前から課題として指摘されているが、「制度が変わるかもしれない」という理由で中期整備計画が進んでいない。
また道路網・河川防災・地域防災公園など、長期投資を要するインフラ整備では、府市の責任分担が曖昧なため、意思決定が遅れている。
一例を挙げれば、淀川左岸線延伸部の整備や夢洲アクセス鉄道計画など、府と市の調整が長期化したことで、工期・コストともに膨らんだ。これらの“時間のロス”は市民生活の利便性を直接削ぎ、民間投資の足も止めた。
同じ期間、福岡市は都心再生「天神ビッグバン」で都市機能を刷新し、人口流入・企業立地を増やしている。大阪市との対照は鮮烈である。
単に開発すれば良い良くないという話ではなく、ビジョンそのものが描かれていないことに大きな問題がある。万博後の夢洲ですら、その方向性は見えていない。
そもそもATCですら遠いと考える大阪市民感覚だが、その先の夢洲の開発は市民生活とはあまりにかけ離れた場所での出来事のようにも感じる。
「中途半端な二重構造」による3重行政
都構想の目的のひとつは、府と市の二重行政解消というお題目であった。しかし、大阪市民にとって本来は選択肢が2つにあることはむしろ豊かであり望ましかったはずだ。大阪市民の公務員嫌いを片手にとり、二重にある行政のしくみを単なる無駄としてしまったが、それ自体がボタンの掛け違いであった。
結局、都構想は頓挫したが、構想が宙に浮いた結果、大阪市政には中途半端な二重構造ができてしまい、むしろ3重行政のような状況に陥っている。
府市統合本部や広域連携局など、暫定的な組織が乱立し、職員は“いつか制度が変わる前提”で動くため、責任の所在が曖昧になった。
市の職員にとっては「どうせ将来は府に吸収されるかもしれない」
府の職員にとっては「いずれ特別区に任せる領域かもしれない」
そんな気分が続けば、政策立案の熱も削がれる。
結果として行政サービスの質が均一化されず、区によって支援内容やスピードがばらつくようになった。
これは住民の体感として「市役所が遠くなった」「相談しても動きが鈍い」という不満につながっている。

都市ブランドの曖昧化と企業・人材の流出
都市の競争力は、明確なビジョンを示せるかどうかにかかっている。
東京が「世界金融都市」、横浜が「ウォーターフロントの国際都市」、福岡が「スタートアップシティ」を掲げるなか、大阪市だけが「都になるかどうか」という制度論ばかりがニュースを占めていた。
その結果、国内外の投資家・企業にとって大阪は「不確実な都市」という印象が根づいているように感じる。
実際、オフィス需要は一時的な景気変動を除けば、東京・名古屋・福岡より回復が遅れ、若年層の転出超過も止まっていない。
住民にとっても「行政の形が安定しない街」に長期的に根を張ることは難しい。
この10年で大阪市の人口は維持しているものの、実質的な増加分は外国人・単身者層に偏り、子育て世代の定着率は下がり続けている。
まちの将来像が描けなければ、企業も人も「いつか変わるかもしれない都市」には腰を据えない。それが大阪市の現実である。
財政・制度の「検討疲れ」と現場の摩耗
制度改編をめぐる議論が長引けば、最も疲弊するのは現場である。
職員は2回の都構想関連の説明会、シミュレーション、住民対応、広報資料作成に膨大な時間を費やした。
そのコストは直接の財政支出だけでなく、行政の改善活動・新規事業開発の機会損失として積み上がっている。
また、「制度が変わるかもしれない」という前提のもとで、人事・組織・予算の中期計画が立てられず、現場は常に“暫定運用”の連続となった。
これは、市の持つイノベーション能力を蝕み、いわば「検討疲れ」という形で職員の士気を下げてしまったのである。
結果として、他都市では官民連携で進むスマートシティ化、脱炭素都市戦略、デジタル防災などの新しい政策分野でも、大阪市は大きく遅れをとっている。
自治の形を問うことと、自治そのものを失うこと
制度をどうするか、という議論は本来、より良い自治をつくるための手段である。
だが大阪では、都構想という「制度論」そのものが目的化し、自治の中身——住民と行政がどう協働するか——が置き去りにされた。
住民投票が繰り返されたことで、市民の間には「もうその話は聞き飽きた」という諦念も広がった。また市民の分断も広がった。自治を議論するはずの過程が、ポピュリズム的な感情論を経て、逆に自治への関心自体も薄れさせたのである。
行政もまた、次の制度改正を待つ姿勢が染みつき、「今できる改革」を先送りする癖がついた。
こうして「決断しないこと」が常態化し、政策の実行力を奪われたまま、10年以上の月日が流れた。
自治とは、制度を待つことではなく、日々の実践によって形成されるものだ。
その基本を見失ったままでは、いかなる制度改革をしても都市は前に進まない。
いま必要なのは意思と行動
大阪市がこの10年で失った最大のものは「決定力」である。
都構想という制度の是非に振り回され、「大阪をどうしたいのか」という意思は今もなお、置き去りにされたままだ。
キャッチフレーズのような耳障りのいい言葉だけが、飛び交っているが、「定数削減」や「身を切る改革」からは、大阪のビジョンメイクはできない。
制度論に終始した10年は、行政のマンパワーを削ぎ落とした。市民は政党が行う政治ショーにうんざりしている。
決断を先送りし続けたこの10年を取り戻すために、今後は、制度論に縛られない大阪のあり方について、次のビジョンを共有していく必要がある。
今の、そして未来の大阪に必要なのは、新しい制度ではなく、自ら方向を決める意思と行動である。
その意思は、大阪市民の自治が礎でなければならない。
<山口 達也>