前回は、都市計画自体が制度から関係を考えるしくみへの転換が必要だと論じた。さらに自治の主体となる私たちも意識の変容が求められていることについて論じる。
所有から関係へ──都市の自治意識の転換点
大阪市のような大都市では、戦後の持ち家政策をベースに「持ち家=定住=自治意識の高さ」という構図が明確に存在した。家を持つ者は、地域の清掃や町会活動に参加し、まちを「自分のもの」として支える意識を育ててきた。
しかし、この所有と帰属の図式は、人口の流動化、ライフスタイルの多様化、そしてオンラインによるつながりの深化によって、「どこに住むか」よりも「どう関わるか」が重要な時代に移行しつつある。
都市の自治を考えるうえで、単に不動産的な所有だけでは語りきれない。むしろ、そこに居る人びとが「関係を所有する」──すなわち、地域に対して自発的に関心を持ち、他者と協働する力こそが、現代都市における自治の新しい基盤となるべきなのであるが・・・。
持ち家と賃貸──「定住」と「流動」の二つの自治感覚
持ち家という住まい方は、現在でも地域自治の要である。住宅ローンを背負い、家族とともに数十年単位で暮らすことは、地域に対しての長期的な関与を約束する行為だった。固定資産税を通じた公共財への寄与、建物維持のための近隣協力、町会活動への参加など、生活と地域が強く結びついていた。
対照的に、賃貸住宅の居住者は流動的である。転勤、進学、家族構成の変化などに応じて容易に住み替えるため、地域への定着度は低くなりがちであるが、その一方で地域に新しい考え方や風を送り込むという作用も併せ持つ。
こうした環境では、「一時的な滞在者」として地域課題に無関心になる傾向が生まれるだが、これは必ずしも個人の無関心を意味しない。むしろ、都市構造が「流動する住民」を前提としていないために、参加の仕組みが存在していないといえよう。
私自身はUR賃貸住宅に住んで30年になるが、地域との接点は極めて希薄だ。地域の町会長が誰なのかも知らない。これが賃貸住宅の現状でもある。
大阪における「借家都市」の系譜と課題
大阪市の主要な住まい方は、戦前からの長屋に始まり、戦後の木賃アパートや文化住宅、団地、そして民間マンションへと変遷してきた「借家都市」であった。
戦災と高度経済成長そしてバブルを経た都市開発は、地縁よりも利便性や経済合理性を優先する都市構造を形成した。
その結果、町会の加入率は持ち家の多いエリアとそうでないエリアでは明確に差が生まれた。また分譲マンションでは管理組合を通じた限定的な自治が生まれたものの、地域単位の共同行動にはなかなか接続できていない。賃貸マンションではその発想自体もなかなか持てない。
この持ち家居住者=自治、賃貸居住者=無関心という構図は、「所有形態に任せている自治」の限界を示している。自治は「土地の上に築くもの」ではなく、「人と人の間に生まれるもの」として再定義されるべき段階に来ている。
関係都市という新しい居住のかたち
ここで注目されるのが、「関係人口」や「関係都市」という概念である。
人々はもはや一つの都市に固定的に住むとは限らない。大阪で働き、和歌山で週末を過ごし、オンラインでは東北のまちづくりプロジェクトに関わる。そうした多拠点・多層的な生活が当たり前になりつつある。
この流動的な関係を前提とすれば、自治とは「住民票のある場所」ではなく、「関心と行動を共有する場所」で発生するものになる。
大阪においても、地元出身者と転入者、賃貸居住者と定住者がゆるやかに交わり、互いの地域経験を交換することで「関係都市」としての力を持ち始めている。
たとえば、オンラインで福島区の地域活動を知った若者が、年に数回現地で清掃活動に参加する。
あるいは、旧市街地の空き家を活用して、まちづくりNPOとシェアオフィスを運営する人々が現れる。
これらは所有を伴わない関与であり、まさに「関係を通じて都市に参加する」新しい自治のあり方である。
ネットワーク的自治──地域を超えるつながり
自治の舞台は、もはや一つの町や自治会に限らない。SNSやオンラインツールの発達により、関心のあるテーマを軸に、地理を超えたネットワーク的自治が形成されつつある。
「防災」「子育て」「エネルギー」「まちの景観」といったテーマごとに、専門知や経験を共有するグループが生まれ、それが現実の地域活動と結びついていく。
大阪市内でも、町会の枠を超えて活動するボランティアやNPOが増えている。
災害時の安否確認をLINEグループで連携する試みや、商店街と学生団体が共同で開催するイベントなど、ネットワーク型の自治が少しずつ根づき始めている。
この動きは、行政の縦割りを超え、個々の関係性を媒介とした「水平的な都市運営」の萌芽ともいえる。
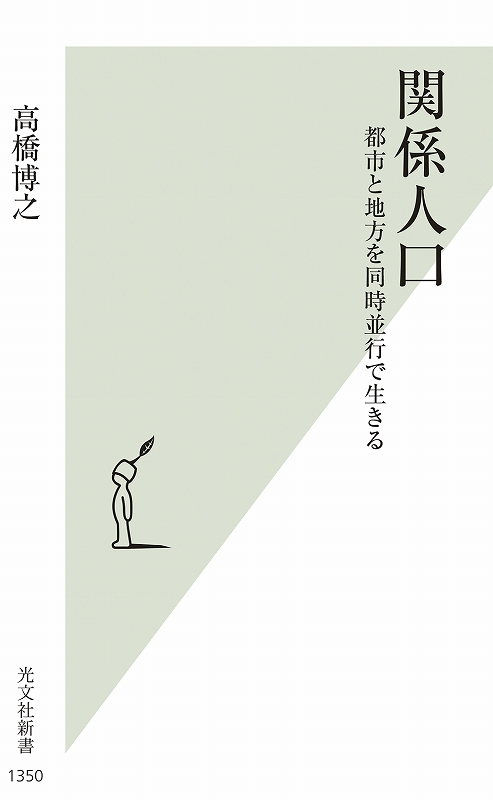
所有を超える自治のデザイン
現代の都市において、所有はもはや「唯一の安定装置」ではない。
むしろ、変化し続ける都市社会のなかで、どのように人と人をつなぎ、共に地域を運営していくかが問われている。
このとき必要なのは、「参加を固定しない自治」である。短期滞在者でも、オンライン参加者でも、地域の未来を語り合い、行動できる仕組みを整えることが求められている。
たとえば、地域通貨やポイント制度を活用し、地域貢献を「可視化」する。
あるいは、行政が町会単位ではなく、テーマ別・関心別に住民を招く新しい協議会を開く。
こうした仕掛けが、持ち家・賃貸といった二分法を越えた「関係の自治」を支える装置となる。
関与が都市を動かす時代へ
大阪の町は、もともと「自分たちの暮らしは自分たちでつくる」という市民自治の伝統を持っていた。
町年寄や五人組の制度、戦後の赤十字奉仕団からをベースとした地域活動に連なる自律的な精神は、今もなお都市の根に息づいている。
ただし、今後の自治は土地を所有する者のものではなく、関係を結び、行動を起こす者のものである。
都市における自治の主語は、「関与者」、あるいは「関係者」である。
持ち家か賃貸かではなく、どのように地域や他者と関わり、何を共有し、どのようにまちを動かしていくか。
この問いを軸に、大阪という大都市が「関係都市」として進化していくことが、ひとつの方向性であることは間違いない。
とともにこの方向は、更なるこれまでの地域自治の衰退と表裏一体である。これまでのしくみと関係都市的自治観をどうミクスチュアしていくのか。ここに大きなヒントが含まれている。
次回は、石巻市で活動している巻組の試みを紹介する。
<山口 達也>



