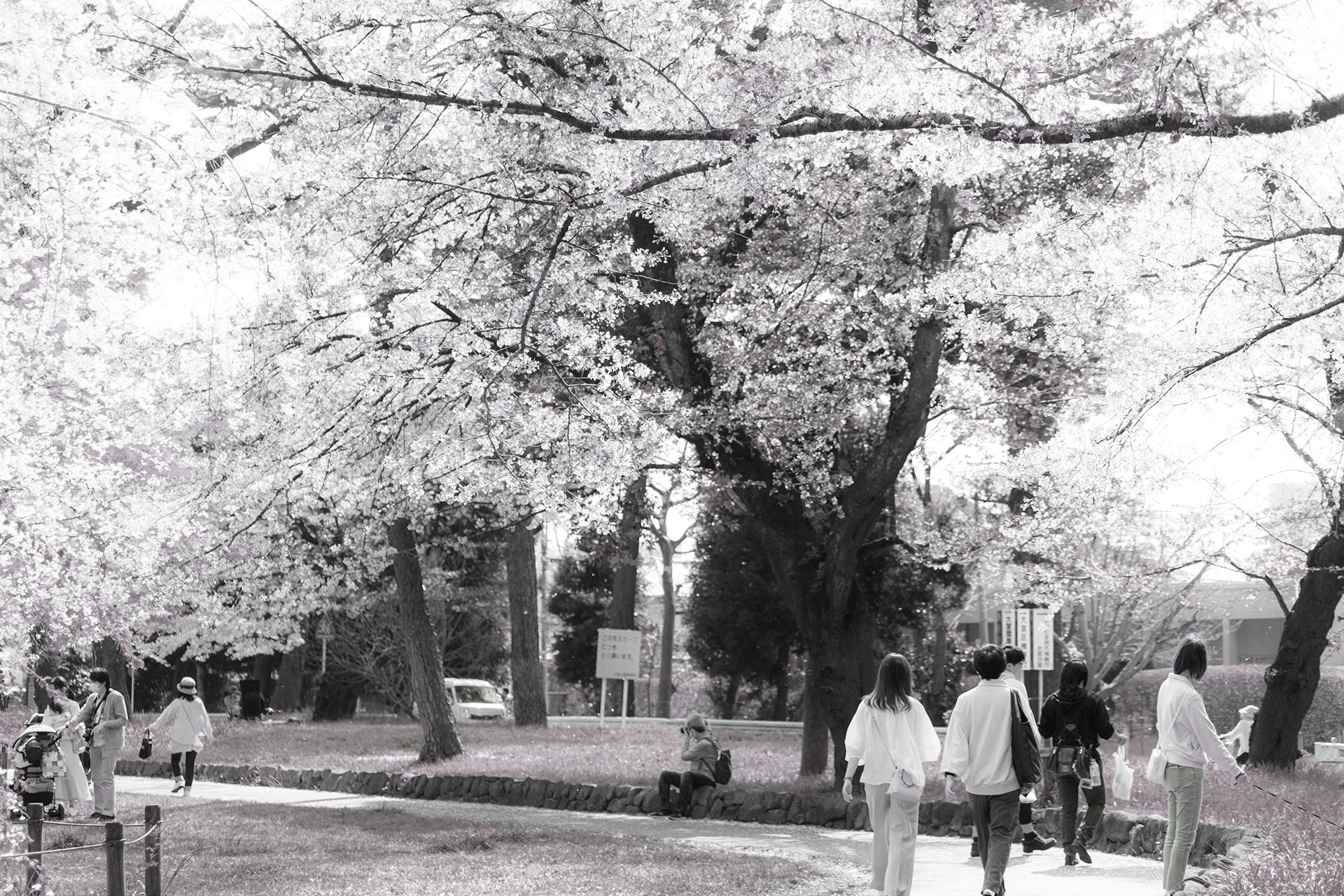共助単位の実例から学ぶ
防災における共助単位は、単なる理論にとどまらず、過去の大災害で現実にどう機能したかを振り返ることによって、その意義と課題が浮かび上がる。
阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの事例は、共助単位の多層性と、その具体的な役割を示している。
阪神・淡路大震災の教訓
1995年の阪神・淡路大震災では、全壊家屋の下敷きになった多くの人々が近隣住民によって救出された。消防や自衛隊の到着を待つ余裕はなく、最初の数時間に命運が分かれた。研究によれば、倒壊家屋からの救助の大多数は住民の手によるものであった。ここで機能したのは「超近隣ミニ班」に相当する関係単位である。
同じ長屋の住人、向かい合う住宅の住人、顔なじみの隣人。こうした数人〜十数人規模の小さな集まりが、瓦礫をどけ、声をかけ、命を救った。人口規模論では説明できない、吉阪隆正が説いた「関係単位」の力が現実となったのである。一方、物資の配布や避難所の開設は小学校区を単位に行われた。つまり初動は小集団、持続は規模単位という二重の構造が浮かび上がった。

東日本大震災における共助
2011年の東日本大震災では、津波災害に直面した。避難の際、高齢者や障害者を支援したのは近隣住民であり、ここでも関係単位が力を発揮した。徒歩圏内での声かけや車での搬送がなければ、多くの命が救われなかっただろう。
一方で、避難所の運営規模は数百から数千人に達し、自治会や小学校区を超える単位での協働が不可欠となった。数日間行政の支援が届かない状況下で、住民自らが避難所を運営し、物資の分配やトイレ管理を担った。ここにはペリーの近隣住区論で示された「小学校区=生活単位」のロジックが生きていたといえる。
さらに、この震災ではSNSや携帯メールといったデジタルツールが初めて大規模に活用された。これにより物理的な距離を超えた新しい関係単位が形成され、情報共有や支援要請に役立った。吉阪の「流動する関係単位」がデジタル時代に拡張されたのである。
熊本地震と仮設住宅
2016年の熊本地震では、連続する揺れにより避難が長期化した。住民は公園や車中に避難し、やがて小学校区の避難所に集約された。避難所運営にはボランティアやNPOが加わり、住民と外部の支援者が一体となる新しい関係単位が生まれた。
また、仮設住宅では入居者同士が新たな隣人関係を築き、共助の基盤となった。日常的な見守りや物資の融通が小集団の中で行われたのである。これは延藤安弘の「小集団開発」の思想が、災害復興の現場で具体化した例といえる。小さな集団が日常を支え、その積み重ねが地域全体のレジリエンスを形成した。
共通する要素
三つの災害に共通するのは、次の点である。
第一に、初動で力を発揮するのは「関係単位」である。数人規模の小さな集まりが命を救い、避難を実現する。
第二に、持続的な運営には「規模単位」が不可欠である。避難所運営や物資配布は数百〜数千人の組織力が求められる。
第三に、小集団は自然発生するだけでなく、計画的に育成することができる。日常のサークルや活動が非常時に防災単位として機能することを、延藤氏の小集団開発論は教えている。
第四に、新しい関係単位が状況に応じて登場する。デジタルネットワーク、ボランティア組織、仮設住宅の隣人関係などがその例である。
学ぶべきこと
以上の事例から導かれるのは、防災共助単位は「規模」と「関係」を二重に重ねる必要があるという教訓である。ペリーの近隣住区論が提供した小学校区単位は、避難所運営や行政連携において依然として有効である。しかし、それだけでは人命は救えない。吉阪隆正氏が説いた関係単位、延藤安弘氏が提唱した小集団の力を重ねることで、初めて実効性が高まる。
災害は社会の脆弱性を容赦なく突きつける。そのとき、助け合いの力を発揮できるのは、小さな関係単位に他ならない。そしてその小集団が重なり合い、制度的単位に結びつくとき、地域全体のレジリエンスは最大化する。
共助単位の実例から学ぶべきことは明快である。数ではなく関係、関係だけではなく規模、その二重の真理を忘れてはならない。
さて、我々はこのような理論や経験値を背景にどんな防災計画を立てるべきなのか。今までの地域防災計画にはこの「関係」の構築がに弱いため、しくみづくりが見えてこないのではないかと思われる。
<山口 達也>