地域の活動を掘り下げるに当たって、どうしても気にかけておきたい課題がある。それが「単位」だ。様々な建築家や都市計画家が100年以上前からどのサイズ・スケールで、仕組みを作っていくべきなのかを模索している。
私自身も建築設計を生業としていることもあり、この「単位」には大きな関心がある。どういった単位で防災共助を組み立てていけばよいのか、この「単位」について取り上げた中編。
吉阪隆正と関係単位の思想
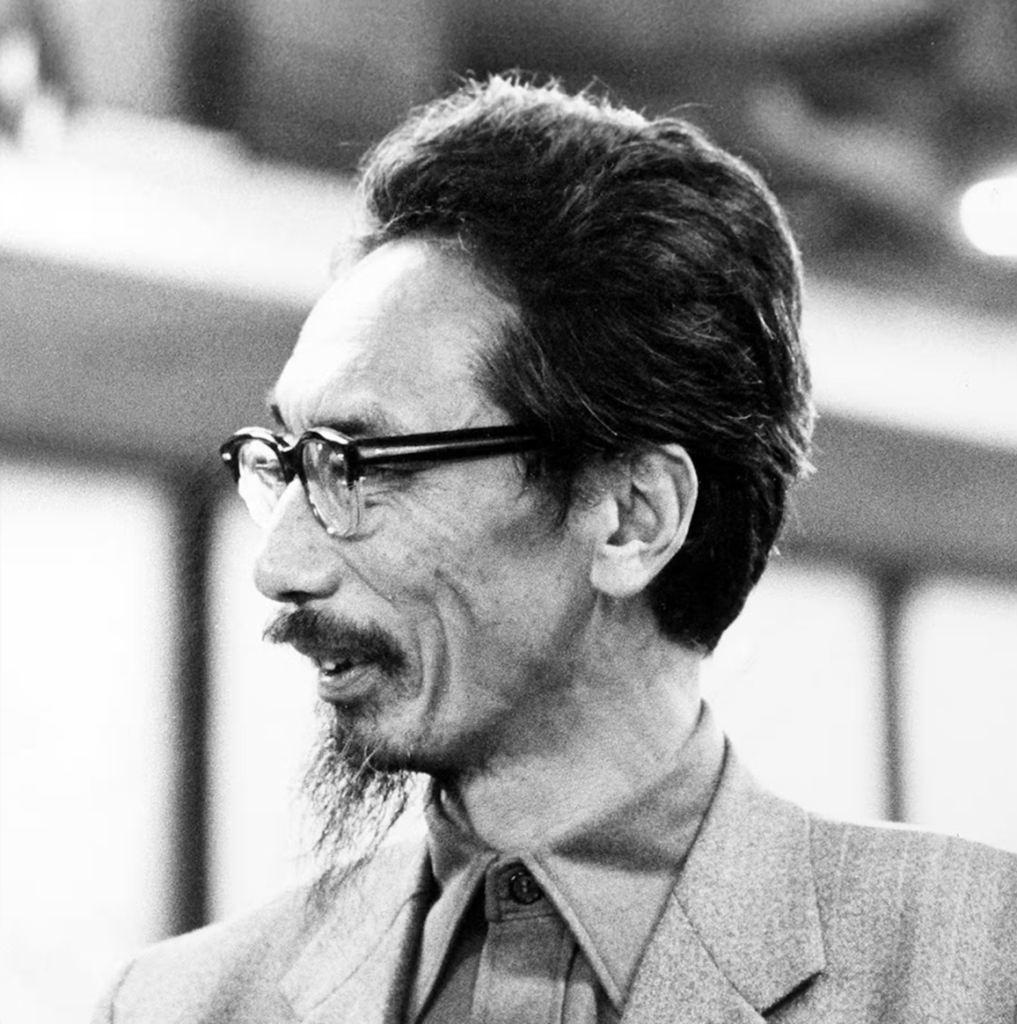
前編で紹介したC・ペリーの近隣住区論による人口規模の考え方に対して、戦後の日本で異議を唱えた建築家・都市計画課の一人が吉阪隆正(1917-1980)である。彼は世界的な建築家ル・コルビュジエに学びつつ、アジアやアフリカの集落を調査し、人口規模で共同体を区切る発想そのものに疑義を呈した。
吉阪が重視したのは「関係単位」である。すなわち共同体は人口数ではなく、関係性と活動によって成り立つという考え方である。数十人でも市場や祭りを通じて社会が維持される集落を観察し、逆に数千人いても関係が希薄であれば共同体は機能しないと論じた。
吉阪の思想は、住むこと、都市、社会はいずれも流動し、固定的な枠でとらえられるものではない。人は複数の関係単位に重層的に属し、そのネットワークのなかで暮らす。ゆえに人口基準で一律に線を引くことは無意味だとする。
この視点を防災に応用するとどうなるか。
まず初動の「超近隣ミニ班(5〜10人)」はまさに吉阪的な関係単位である。顔が見えるから助け合える。数ではなく関係こそが命を救う基盤になる。
次に自治会や小学校区はペリー的な規模論の単位である。これを行政と結びつけることで持続性を確保できる。すなわち防災は「吉阪的関係単位」と「ペリー的規模単位」を重ね合わせた規模論が求められていると考えることが妥当なのではないか。
多くの関係性で醸成される都市型コミュニティ
現代ではこのように様々な関係性を持っていることがますます重要となっている。小学校区の衰退、都市構造の変化、デジタル通信の普及は、人口規模の単位だけでは対応できない。むしろマンションのフロア単位やLINEグループ、こども食堂でのネットワークといった小さな関係単位が、防災共助の初動を支える現場の力となる。
吉阪隆正の思想は、防災における「顔の見える小さな関係単位」の価値を再確認させる。人口規模で区切るだけでは実効性が乏しい。
しかし一方で規模単位も行政運営には不可欠である。
だからこそ、防災単位論は「規模」と「関係」の二重構造を設計しなければならないのである。
防災単位論への展開
以上の内容を表にしてまとめた。
ペリーの近隣住区論は現在の日本の都市計画の礎になっているが、その上で関係単位という概念を用いることで有効な防災単位という認識があらためて構築できうるのではないかと考える。
| 観点 | ペリーの近隣住区論(1920s) | 吉阪隆正の批判・思想(1950s〜) | 防災単位論 への接続 |
|---|---|---|---|
| 基本発想 | 人口規模で生活単位を計画 | 人間は数ではなく関係で結びつく | 両者を重層化(規模単位+関係単位) |
| 中核施設 | 小学校(約5,000〜9,000人に1校) | 「核」は固定施設ではなく、活動や関係によって生成 | 防災では避難所=小学校を核に、関係単位(ミニ班)を補完 |
| 距離基準 | 徒歩圏400〜800m | 固定距離ではなく、集落の文脈や地形に依存 | 一次集合:徒歩5分(関係単位)、二次集合:校区(規模単位) |
| 生活単位 | 近隣住区(neighborhood unit)=数千人規模 | 「ムーブマン」=流動する人間集団 | 防災単位は状況に応じて可変(救出時は5人、避難所では数千人) |
| 計画姿勢 | 上から与える規模設定 | 下から生成される共同性 | 住民提案型「地区防災計画」と親和性 |
| 弱点 | 人間関係の実態を軽視/形骸化の恐れ | 規模の操作性を欠く/行政運営と噛み合いにくい | 規模論+関係論のバランス設計が不可欠 |
更に展開した延藤安弘「計画的小集団開発」
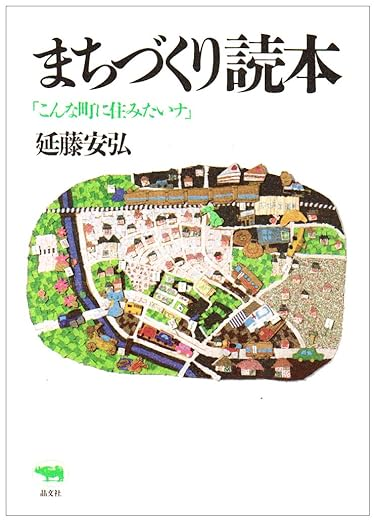
延藤安弘(1940-2018)は、戦後日本の住宅やまちづくりにおいて「小集団」の重要性を繰り返し説いてきた建築計画研究者である。大規模な団地やニュータウン開発が進められる中で、彼は「人が人らしく生きるためには、大きな枠組みではなく、小さな集まりを基盤に据えることが不可欠である」と語っている。その考えを「計画的小集団開発」と呼び、これを「これからのいえづくり・まちづくり」の基本姿勢・基本単位として提案してきた。
小集団とは、数人から十数人程度の顔が見える集まりである。そこには名前を呼び合い、対話を重ね、生活上の困りごとや喜びを共有できる関係がある。
彼は「人が安心して暮らすには、まず小さな関係の場が必要である」と繰り返す。大規模な計画やハード整備が先行しても、生活の基盤となる小集団が育たなければ、街は人間的な魅力を失ってしまうのである。
この「計画的小集団開発」は、単なる自然発生的な寄り合いではなく、意図的に小さな集まりを計画の中に位置づけ、育てていこうとするものである。住棟ごとの談話室や集会所、街区ごとのポケットパークや共用スペースといった「小さな場」を意識的にデザインし、そこに日常的な集いが生まれるようにする。その積み重ねがやがて地域全体を支える関係資本となる。延藤氏が重視するのは、「小さな関わりが大きな共同体を育てる」という逆ピラミッド型の発想である。
「計画的小集団」という防災単位
この思想は防災の世界に直結する。防災の初動は、行政や大規模組織ではなく、隣人同士の声かけと助け合いから始まる。倒壊家屋からの救出の大部分が近隣住民によって行われた阪神・淡路大震災の教訓はよく知られている。まさに小集団が命を救う最前線だったのである。
防災単位の階層構造を見れば、最小単位は5〜10人の「超近隣ミニ班」である。これは彼のいう小集団と完全に重なる規模感である。平時には清掃活動や子育てサークル、趣味の会などの小さな活動を通じて関係を育み、非常時にはそのまま防災班として機能する。つまり「小集団開発」は、防災共助単位を日常から立ち上げる実践的手法になる。
さらに、小集団をいくつも積み重ねてネットワーク化すれば、近隣ブロックや自治会といった中規模単位につながる。そして最終的には小学校区=避難所圏域という制度的な単位へ接続する。
ここで行政との連携が可能となり、公助を呼び込むことができる。防災の重層構造は、まさに延藤氏が描いた「小集団の積み重ねが大きなまちをつくる」という構造と一致している。
現代の都市では、自治会の加入率低下や人口流動化によって、従来の単位が弱体化している。その中で「小集団」を基盤とするアプローチはますます重要性を増している。マンションのフロア単位、LINEグループ、子ども食堂や居場所づくりの活動などは、延藤的な小集団の現代版ともいえよう。
これらは行政制度に直結しないが、災害時には確実に役立つ共助単位となる。
延藤氏が語ったのは、人間らしい生活の場をどう再生するかという問いであった。だがその思想は、防災の現場で「命を守る最小の仕組み」として生き続けている。小さな集まりを計画の中に組み込み、育て、重ねること。
そこからでしか、持続可能で人間的な地域防災は構築できない。
<山口 達也>



