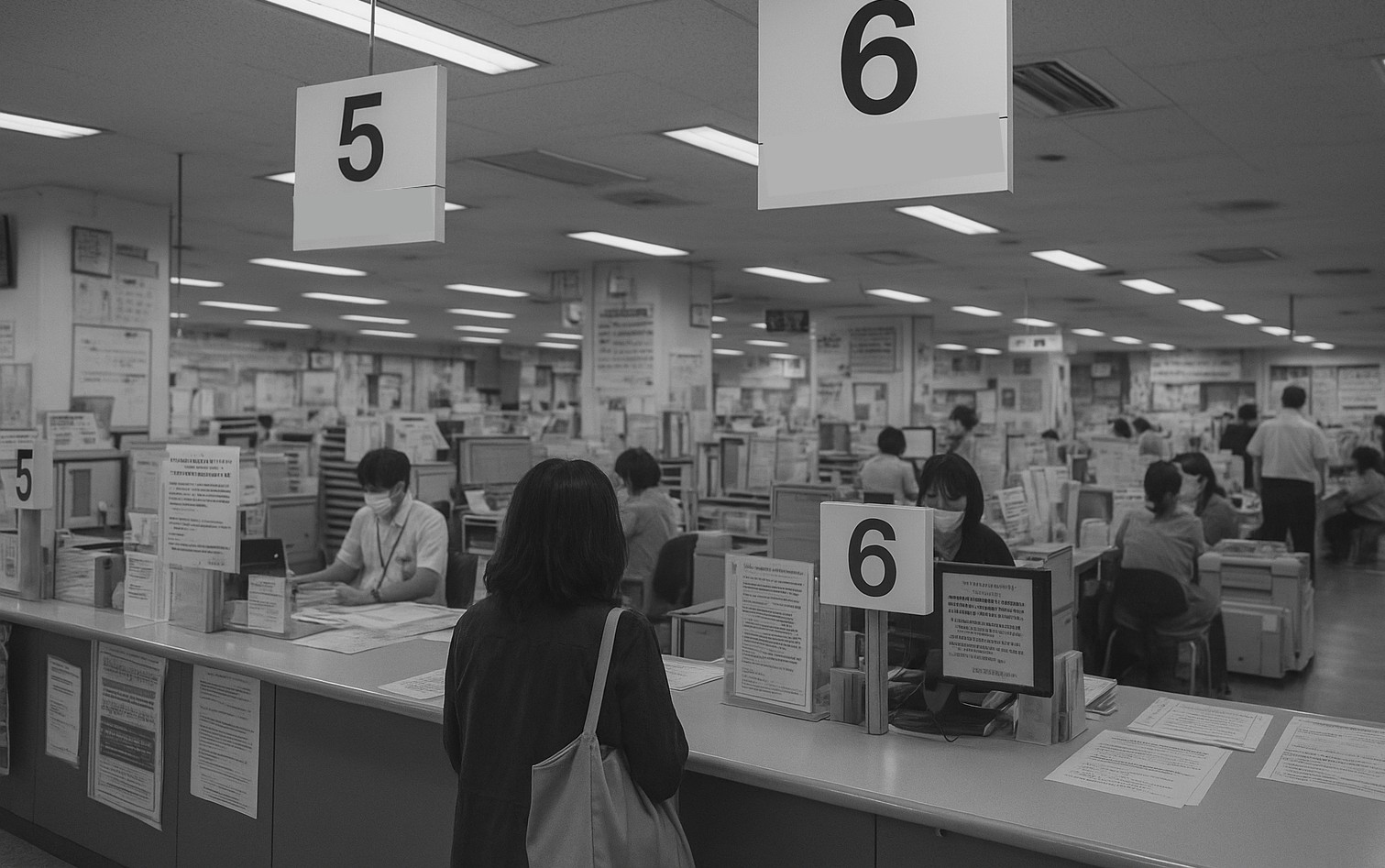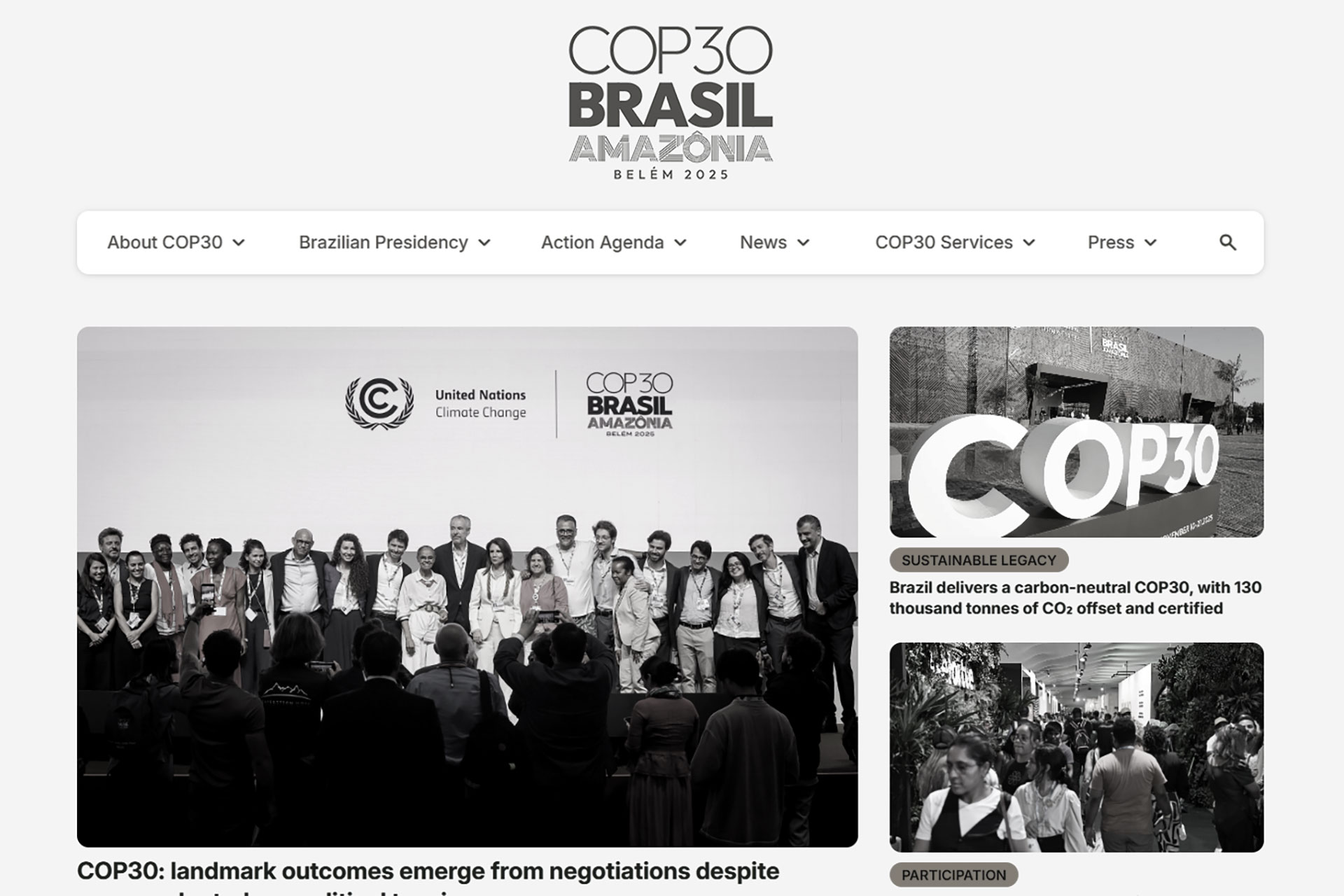縦割り行政という昭和の遺物がゴロゴロ転がっている
正直に言えば、いまだに「◯◯課へ行ってください」「それはうちの所管ではありません」と言われるたびに、昭和の亡霊に追いかけられているような感覚になる。
住民としても、行政に関わる仕事をしてきた身としても、ここはもう令和であり、「なんで一回で済まないの?」が当たり前なのに、まだ“縦割り行政”は盤石のままである。
しかし、そんな中で全国を見ると、ポツリポツリと“ワンストップ行政”の成功モデルは実際に存在する。「市役所のどこに行っても、案内一つで全部通してくれる」「書類が一体化されている」「市民ポータルで簡単にできる」。
ではなぜ、それが全国で広がらないのか——今日は自分の視点でその理由を考えてみたい。

「タテ社会の人間関係」は欧米の契約精神に基づいた考え方とは、全く異なる日本社会の人間関係を分析し、当時大変話題になったテキストである。
しかし今読んでも、「場」「ウチソト」を考える日本的社会構造の分析はむしろ新しく感じる部分も多い。
この縦割り行政は、昭和・令和ではなく、日本社会に強く根付いている文化そのものなのかもしれない。
なぜワンストップ行政は広がらないのか
行政の階層構造の深すぎる文化
行政は“組織のDNA”が縦に積み上げられている。
国から来た通知は縦方向に落ち、各課は各課の専門性に基づいて仕事を積む。
よく言われる「横串」は、そのたびに“例外処理”として扱われる。
言ってみれば、全国の自治体は「縦型のアプリ」を延々バージョンアップしているようなもので、根本構造を変える“フルリプレイス”は誰も手を付けられない。
だから、ワンストップ行政のような“UI/UXの全面改修”が広がりにくいのである。
成功自治体の積み上げ大でパッケージ化が困難
ワンストップ化を成功させている自治体を見ると、必ずと言っていいほど「担当者の粘り」「地域事情に合わせた丁寧な改善」「市民との対話」がセットになっている。つまり、そこには“人の熱量”が強く影響している。
だが、それゆえに逆説が起こる。
- 成功モデルがローカル仕様に最適化されすぎている
- その自治体の人材や文化が前提になっている
- ほかの自治体には移植しにくい
全国展開すべきと思えるモデルほど、「その街だからできた」感が強いのである。
行政改革は“痛み”を誰が引き受けるか問題
ワンストップ化とはつまり、既存の業務フローの再編成である。
- 課の役割を再整理する
- 権限や担当範囲を組み替える
- 書類の統合に伴い、責任の所在も再調整する
これらは組織の“痛点”に直結する。
つまり、誰かの仕事が変わる、消える、または新しい領域が増える。
人事制度の壁がある限り、そこに踏み込める自治体は多くない。
そして実際、多くの自治体で聞く声はこうだ。
「良いとは思うが、うちがいまやる体力がない」
住民が“縦割りの不便さ”に慣れすぎ
意外に見過ごされがちなのがこれである。
日本の行政サービスの基本品質は高い。そのため、不便を“我慢できてしまう”。
役所が悪いというより、国民の我慢力が高すぎると言った方が近い。
もし「不便は不便」とはっきり言う文化が行政を動かす可能性があるが、今はまだ過渡期である。
ワンストップ化自治体」と「不可自治体」の差
できる自治体
- 現場主導で小さく始める
- 市民の体験(UX)を重視
- 1課の改善ではなく、庁内横断チームが機能する
- “既存の基準”を神聖視しない
- ICT推進室が実権を持つ
できない自治体
- 全庁一斉でやろうとして動かなくなる
- 各課調整が延々と続き、誰も決めない
- 住民の声が届きにくい
- ICTは導入するが、業務プロセスはそのまま
- 予算要求が「従来通り」の枠組み
この差は、行政といっしょに仕事をしていると痛いほど感じる。
ではどうすれば良いのか
“縦割り行政を壊す”のは、まるでレゴブロックを分解して組み直すようなものだ。
個別ピースのままでは何も変わらないが、組み直せば全く違う風景が見える。
そのために必要なのは、次の三つだと思う。
① 行政内部に「体験設計(UX)の観点」を入れること
行政は論理で動くが、住民は体験で動く。本当はこの距離が一番大きい。
② 改革を“人”に依存しないための仕組み化
特定の人の熱意で進むモデルは一代限りで終わる。全国展開できるのは“仕組み化”されたものだけだ。
③ 成功モデルを「移植可能なパッケージ」にする
民間のように、自治体も“セットアップすれば使える”形が必要である。
本気でやるなら、国主導でコード化したほうがいい。
縦割りを越えるために
若者にとっては「役所で何度も窓口を回る」のはすでに異世界の文化であろう。
ならば逆説的であるが、彼らが当たり前だと思う世界に行政を合わせることが、実は一番の近道ではないか。
昭和のルールで作られた行政を、令和の感覚で再構築する。
それは、誰か一人の作業ではなく、この社会全体のアップデート作業である。
私はその変化の途中に立っている。
だからこそ、「まだ変わる余地がある」という希望を捨てずにいたいと思うのである。そう考え希望を持ったほうが、心身の健康にはいいに決まっている。
でも大阪の区役所はどう変えられるのだろうか。
<山口 達也>