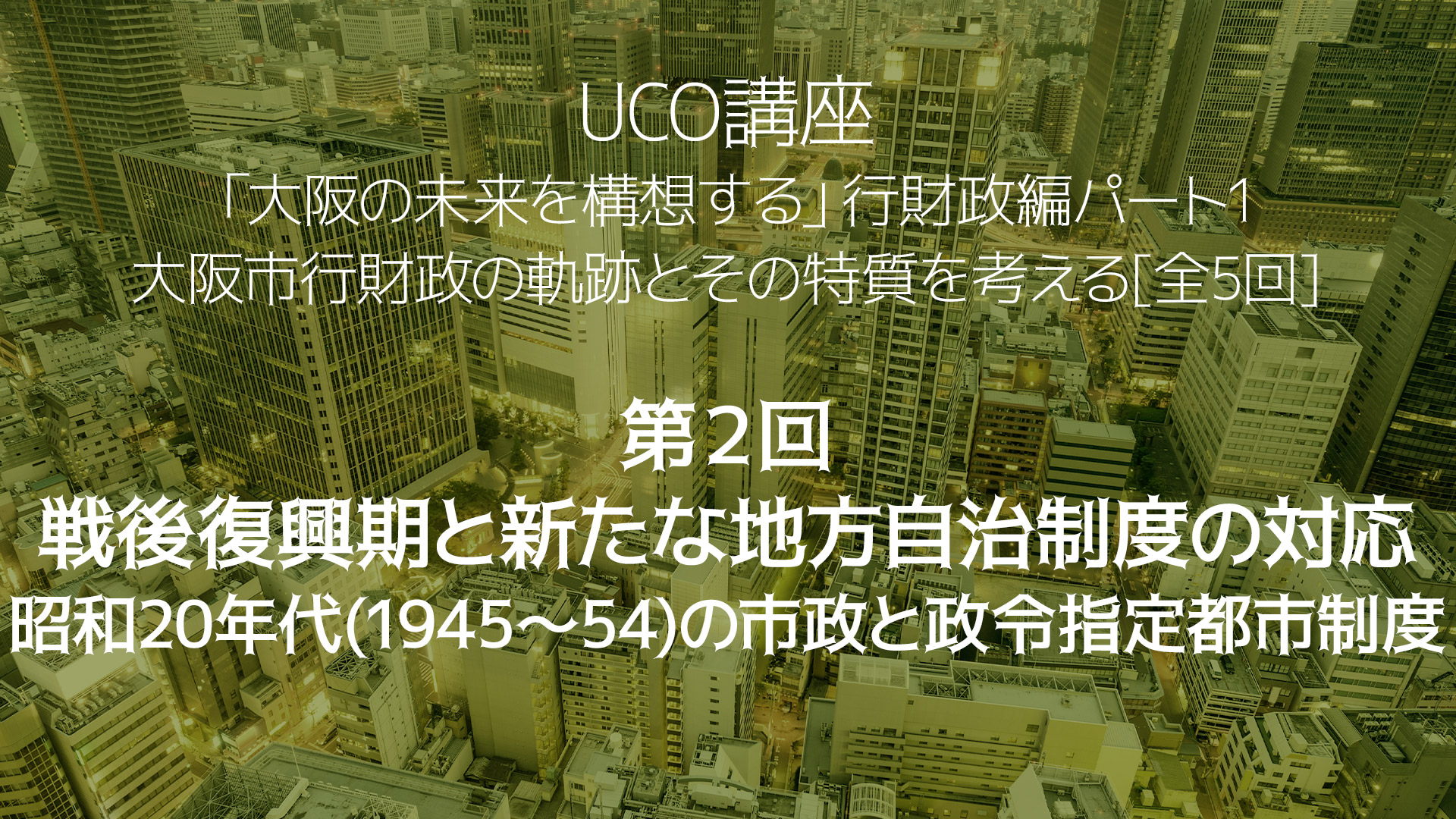はじめに:震災から立ち現れる自治の原型

2025年、阪神・淡路大震災からちょうど30年を迎えた。1995年1月17日、6434人の命が一瞬にして奪われたあの震災は、都市型直下地震の脅威をまざまざと見せつけたと同時に、日本社会に「ボランティア」という新たな市民主体の行動形態を刻み込んだ。「ボランティア元年」とまで称され、行政だけに依存しない住民と市民の協働こそが、有事における新しい社会の姿を体現したのである。
あれから30年。果たしてその経験は、現在の社会に根付き、機能しているのだろうか。単に記憶のアーカイブとして保管されるのではなく、構造として防災・減災の体系に織り込まれているのか。次なる巨大災害が確実視される現在において、「防災」という課題は「自治」の再定義と不可分である。この問題意識を出発点に、数回にわたり、「防災の観点から自治を再構成する」意義を掘り下げていきたい。
災害関連死の衝撃——熊本地震の教訓

2025年、阪神・淡路大震災からちょうど30年を迎えた。1995年1月17日、6434人の命が一瞬にして奪われたあの震災は、都市型直下地震の脅威をまざまざと見せつけたと同時に、日本社会に「ボランティア」という新たな市民主体の行動形態を刻み込んだ。「ボランティア元年」とまで称され、行政だけに依存しない住民と市民の協働こそが、有事における新しい社会の姿を体現したのである。
この数字は、震災対応の重点が「地震の瞬間」に集中しすぎており、被災後の生活フェーズにおける支援体制が極端に弱いことを物語っている。災害の本質は、発災の瞬間のみならず、その後に続く数日、数週間、さらには数か月という生活空間の持続可能性にある。つまり、自治体のインフラ整備や耐震構造だけでは足りない。必要なのは、地域に根ざした「生き延びるための関係性」とその体制づくりである。
津波避難ビルの実相——指定と現実のギャップ

筆者が住む大阪市此花区は、南海トラフ地震による津波被害が確実視されている地域であり、集合住宅が「津波避難ビル」に指定されている。このような指定自体は、行政がリスクを把握し、初動を想定して計画を策定している証左であり、評価に値する。
しかしその実態には、大きな不安が残る。津波が引くには数日を要するとされ、その間、避難してきた地域住民はどこで、どう過ごすのか。
指定されたビルの外廊下はコンクリート剥き出しで、十分な居住性もなく、プライバシーや寒暖対策、衛生面にも問題がある。水・食料・簡易トイレの備蓄も不十分であり、現実には「避難すること」が命を守るどころか、災害関連死の温床になる可能性さえある。
このような状況で最も問われるのは、「誰が避難者を受け入れるのか」「誰がマネジメントするのか」という視点である。行政は避難ビルの指定まではするが、そこでの生活維持や人間関係の摩擦に関与しない。その空白を埋めるのが、地域住民自身の自治能力なのである。
野田地区の取り組み——防災士育成の限界と可能性
大阪市福島区・野田地区では、町会費を使って住民に防災士資格の取得を促す取り組みが行われている。これは「自助・共助」の精神を育むうえで有効な手段であり、学びを通じて防災の基本知識を共有できる貴重なモデルといえる。
しかし一方で、この地域に何人の防災士がいて、どのような技能を持ち、どこに配置されているのかという基本情報が共有されていない。人材の「見える化」がなされていなければ、いざというときに彼らがどのように動くのか、周囲が誰を頼ればいいのか判断できない。
制度を導入するだけでは意味がない。その制度を地域の「構造」として機能させるためには、ネットワーク化、役割分担、情報共有といった「組織化の力」が不可欠である。防災士は点であり、これを線と面に変えるには、自治的運用力が問われている。
世田谷のラウンドテーブル——「緩やかな共助」という新しい自治のかたち
東京都世田谷区のとある地区では、行政・警察・消防・社会福祉協議会といった公的機関に加え、地域の自治会、子ども会、商工団体、医師会などが、ラウンドテーブル形式で定期的に防災会議を行っている。
この形式は、従来のように行政が一方的にハンドリングするものではなく、地域住民と専門機関が対等な立場で、情報を持ち寄り、議論し、連携体制を柔らかく構築する手法である。ここでは、防災計画にとどまらず、高齢者の見守りや避難所の運営、子どもの保護体制に至るまで、日常的なつながりが災害対応力を底上げする。
このような緩やかなネットワークは、地域防災の強靭化のみならず、「自治」の再生を促す機会ともなる。形式的な協議体ではなく、実効性のある関係性の再構築がここにある。
地区防災計画の意義——再構成のための道具として
内閣府は「地区防災計画制度」を整備し、住民主体による防災計画の策定を促進している。これは、「その地域にどのような災害が起きうるか」「そのとき、自分たちは何をするか」を住民自らが議論し、文書化しておくものである。
この取り組みは、計画そのものよりも、住民が主体的に話し合い、協働するプロセスに価値がある。形式的に文書を作成して終わるのではなく、その計画が住民にとって「自分ごと」となるような関与の設計こそが、自治再構築の第一歩となる。
▶ 内閣府 地区防災計画サイト:
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html
締めくくりに——再構成は「当事者になる」ことから始まる
防災の観点から自治を再構成するとは、単に役所の支援を待つことでも、防災グッズを揃えることでもない。自分たちがこの街で、誰と、どう生き延びるのかを考えることから始まる。そこには制度設計以上に、意志と関係性が求められる。
次回は、避難所運営を通じて、「防災とコミュニティ」というテーマを掘り下げる予定である。避難所に求められるのは、設備か、それとも人とのつながりか——その問いが、自治の再構築に新たな視座をもたらすであろうと考えている。