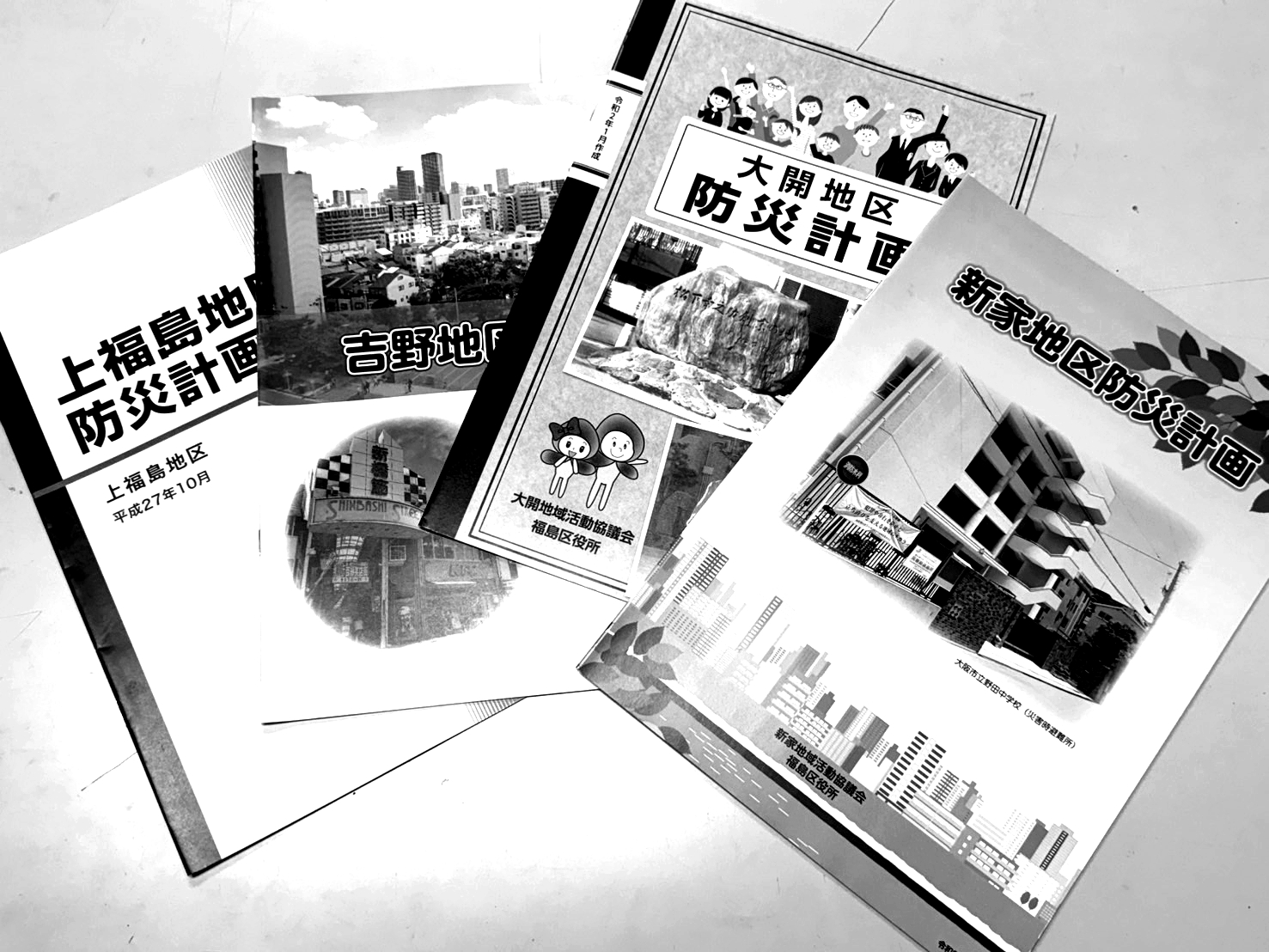vision50の防災からは、これまでの概論から、実際に地区防災計画を作っていくということに段階を移していきたい。そのために必要な視点は、地域から何を積み上げていくのかという点と、内閣府からの「みんなで作る地区防災計画」というトップダウンだ。その3話目。
地区防災計画書の現状
そもそも地区防災計画制度は、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災の教訓を受けて、地域住民及び事業者による自発的な防災活動を促進するために2013年の災害対策基本法改正により、地域防災力の向上を図るために制度が創設され、2014年(平成26年)4月から施行された。
地区防災計画の多くがそれ以降に雨後の筍のように作られているにはそういう理由なのである。
大阪市福島区の場合、平成27年から令和2年で全10地区(10町会)の地区防災計画が作られらた。そろそろ10年経つものもあるわけだが、その内容は平成27年版と令和2年版についてはほとんど同じ内容で、フォーマットと印刷が異なるだけ。むしろここまで同じなら全く同じものを作ればいいはずなのだが、大阪市政のやる気の無さを感じる。
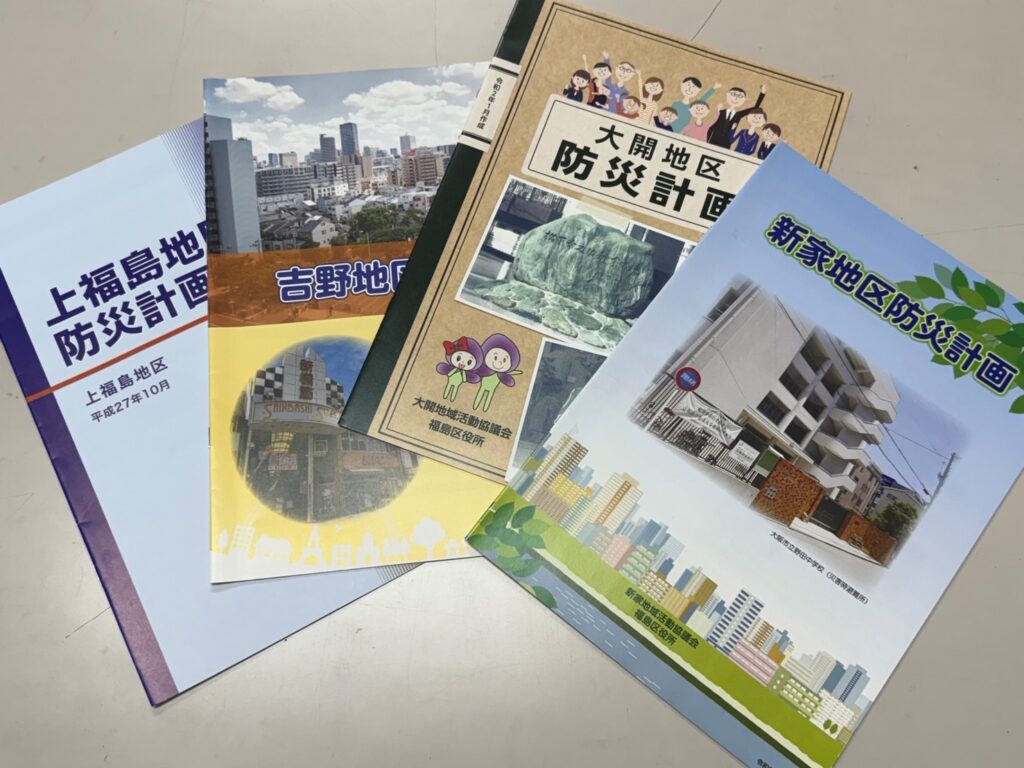
そのやる気の無さが私たちの危機意識の源にあるわけだが、地区防災計画のリニューアル版をつくる場合、既存の計画=行政が用意したフォーマットや例文集をすっ飛ばすわけにはいかない。
「なんだか堅苦しい表現」だと感じるかもしれないが、むしろ、行政の雛形を“たたき台”として利用するのが賢いやり方ではないだろうか。雛形があるおかげで、どこに何を書くべきかの道筋はすでに示されているからである。
地図と雛形と
前回で描いた地図は、すでに地域の危険箇所や資源を反映しているであろう。この地図を横に置きながら雛形を埋めていけば、単なる行政文書ではなく“町の実感”が入った計画になるはずである。「避難所運営」にはどの場所が該当するのか、「安否確認」にはどの通りや班が担当できるのか。地図を見ながら書き込めば、机上の文章が現実の動きと結びつく。
実際に、大阪市福島区野田地域では、地域のボランティアによって、防災マップの見直しを5年前に行っている。

役割に人名を
この雛形には「避難誘導班」「物資調達班」などの項目が並んでいる。そこに実際の名前を入れてみるとどうだろうか。名前が入った瞬間、計画は抽象的なものから、誰かが責任を持つ具体的なものに変わる。もちろん「仮」で構わない。「〇〇さんならやってくれるのでは」という期待値を書き込むだけでも、一歩前進といえるのではないだろうか。
ただし、この「人振り」は一歩間違えると、単に責任のなすりつけになってしまう。最近、NHKのクローズアップ現代で町内会が特集された。役員の8割が、辞めたいと思ったことがあると回答。ボランティアで活動しつつ、責任だけがのしかかる不合理さに多くの町内会の方も悩んでいるのだ。
「町内会が消える?〜どうする 地域のつながり〜」 – クローズアップ現代 – NHK
ものごとをすすめていくには、責任の所在を明確にするために役割分担が不可欠だが、これは業務ではない。仕事でない以上、この「人振り」には課題が残されている。
わからない点は「行政に調べてもらう」
雛形の中には、住民だけでは判断しにくい部分も出てくる。たとえば「避難所の開設権限は誰にあるか」「行政備蓄は何日分あるのか」といった情報は、行政に確認しなければならない。無理に空欄を埋める必要はない。むしろ「行政に調べてもらうリスト」としてまとめれば、次の打ち合わせで担当者に答えてもらえるはずである。
ここで「はず」と書かねばならないところに今のマンパワーを削減された大阪市政の厳しさがある。約8万人の福島区で担当が2人。
だがここはシノゴノ言っていても始まらない。自治とは、地域でできることと行政でできることを明確にし、その間を埋めていきつつ協働することなのであるから、わたしたちも積極的に行政にからみ直さねばならない。
行政説明会を「町会案プレゼンの場」に変える
行政が開催する防災訓練や説明会の場は、本来なら「行政が教える場」である。しかし、そこに住民側の“地区防災計画の町会案”を持ち込めば、逆に「住民が発表する場」ともなる。雛形を自分たちの言葉で埋め、地図を添えて行政に提示すれば、「このエリアはここまで考えている」ということも伝えられる。
そこまで地域が力をつけるには数年かかるかもしれない。
行政の権威を借りながら、実は住民主体の計画が前に進む。これこそ地区防災計画に求められている重要な機能なのだ。
完成度より「形にする」ことが大事
この段階で作る計画は、あくまで原型をリニューアルした「第1版」である。完成度を求めすぎる必要はない。まずは形をつくり、行政に提出・提案できる状態にしてしまうことが大切だ。出してみて初めて課題が見えるし、修正はいつでもできる。むしろ、計画は更新を前提に動かすべきものなのだから、「第1版を世に出す」こと自体が重要な一歩なのではないだろうか。
行政の雛形に振り回されるのではなく、それを逆手に取って「町会仕様」に変えていく。このプロセスを通して、地区防災計画は“行政文書”から“自分たちの取扱説明書”へと姿を変える。チッキからのボトムアップをうまく使えば、住民の主体性はむしろ強く育つのではないだろうか。
次回は、この計画を“紙”から“動き”へと進める段階に入っていく。
<山口 達也>