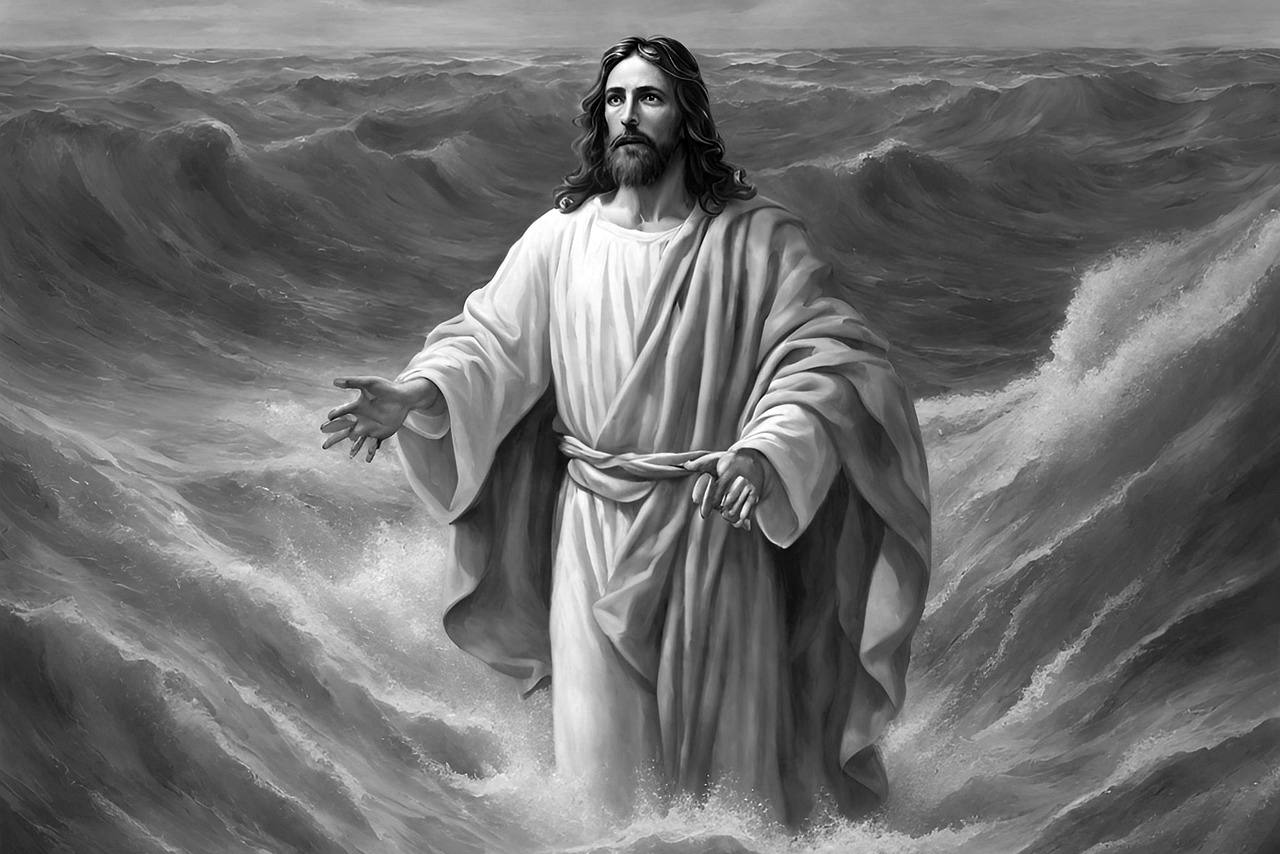大阪カジノ住民訴訟で揺れる夢洲-3
現在進行中の夢洲カジノ訴訟。前回までにご紹介した通り、すでに3年間以上にわたって複数の事件が絡み合いながら原告・被告それぞれの主張が繰り返されている。今回は、第1グループが最初に提訴した第1事件「夢洲IR差止訴訟」について、原告が指摘している違法性について、訴状に沿って見ていこうと思う。
まず、原告団の請求内容についておさらいしておこう。
2022年7月29日に提起された訴訟で請求した内容は以下の3点となる。
- IR事業者である大阪IR株式会社と、事業用地の借地権設定契約を締結してはならない
- 大阪IR株式会社との間で、事業用地について、大阪市が土地所有者の責任としてIR事業のために必要な土壌汚染の除去、液状化の防止、地中障害の除去その他の土地改良費用を負担する旨の合意を締結してはならない
- 事業用地の土地改良事業のため、大阪IR株式会社に対し、一切の支払いをしてはならない
1つ目は、大阪市は、カジノ事業者カジノ用地を賃貸する契約をするな
2つ目は、大阪市は、カジノ用地の土地課題対策の費用*を負担する契約をカジノ事業者とするな
3つ目は、大阪市は、カジノ用地の土地課題対策の費用の支払いを1円もするな
というものだ。
※土地課題対策の費用
カジノ事業者の要請に従って、土壌汚染の除去、液状化の防止、地中障害の除去その他の土地改良費用を指す。大阪市会が約788憶円の支出を採択している。
カジノ事業者への特別待遇は自治体の行為として許されない
この住民訴訟の焦点は、約788憶円という巨額な税金をカジノ用地の土地課題対策費としてカジノ事業者に支払うということを決定したことの違法性を問うところにある。
前回ご紹介した通り、大阪市が埋立地を売却あるいは貸与する場合、これまでは現状有姿を原則とし、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わないことを条件としてきた。この原則に反し、カジノ用地に対して「土地所有者責任」という言を弄してカジノ事業者に逃げられないために巨額の税金支出を決定した。特定の民間企業(ここではカジノ事業者)を優遇する行為は、自治体行政として平等原則(憲法第14条「法の下の平等」)に反している点を追及している。
788億円という巨額の税金支出が予想されている
カジノ用地の賃貸契約と共に締結される「土地所有者責任の合意」では、大阪市が土地課題対策の費用を負担することを前提としている。その費用については、大阪市の積算として788億円を見込んでおり、令和5年度から令和15年度までに788億円を支出することが予定されている。
この指摘に対し大阪市は、カジノ事業者から将来の賃料収入(880億円)があることを引き合いに採算性を主張している。一方原告は、この賃料が収入が果たしてカジノ開業後30年間にわたり、継続的に大阪市に対して支払われる担保はないとし、事業が開始されなかった場合には、支出の回収が全くできない場合もありうるとしている。
カジノ事業は大阪市港営事業の目的ではなく違反している
大阪港湾局(契約者は局長)が本件借地権設定契約、土地所有者責任の合意等を締結することは、カジノ事業者の事業に手を貸すことであり、民間事業者に対する特別の便宜供与にあたる。しかもカジノ事業は、大阪港湾局の目的(大阪市港営事業)に反しており、違法だと原告は主張している。しかもその費用負担は、788億円と巨額である。
また原告は、地方公営企業の独立採算制に反することも指摘している。大阪港湾局が土地課題対策の費用788億円の支出を行うことは、令和2年度末時点で1,414億円の未処理欠損金(赤字)を抱えている大阪市港営事業会計の独立採算制を著しく害することになるという。独立採算制のもとでは、受益者負担が原則である。しかしカジノ事業による長期継続的な事業を前提とした長期の賃料収入が、地方公営企業法上の受益者負担であるとすることはできない。この点が地方公営企業の独立採算制に反する脱法であると指摘している。また、大阪市港湾局の脱法行為を回避するために、大阪市の一般会計から実質的(間接的)に支出するとすれば、それ自体が地方公営企業の独立採算制に反する脱法であるとしている。
土地課題対策費用の将来的な負担増が見込まれる
基本協定書(大阪市とカジノ事業者による土地の賃借契約)を読み解いていくと、土地所有者責任の合意では、カジノ用地に対する土地課題対策費を無制限に負担せざるを得ない内容となっている。そのため、土地課題対策費用はこんごカジノ事業者が必要だと要求すれば、今以上の負担が発生するような契約を結ぶことになる危険性を指摘している。
少し長くなるが、訴状内の該当部分を要約すると、以下のようになっている。
土地課題対策について大阪市は、「当該土地課題対策の実施に実務上合理的な範囲内において最大限協力する義務を負う」としている。最大限協力義務の内容として「市が合理的に判断する範囲で当該費用を負担すること」を定めている。つまり、土地課題対策の実施において必要な限り、その必要性に合理性があれば、金額の多寡は問わないことを示している。大阪市が債務負担行為としては「予算に定めた事項、期間及び限度額の範囲内」など、一定の上限があるように見える。しかし、基本協定書では、土地課題対策費が第2項の債務負担行為で定めた限度額を超えた場合の大阪市の免責には全く言及していない。土地課題対策費が第2項の債務負担行為で定めた限度額を超えた場合、大阪IR株式会社は、大阪市に対して、最大限協力義務の履行として、追加の債務負担行為と支出を求めることができる。
加えて次のように指摘されている。
大阪市の積算する土地課題対策費は、合理的な積算根拠が明らかにされていない。
とりわけ、土壌汚染についての合理的な調査及び当該調査に基づいた汚染除去等の処理費用の積算が行われていない。
大阪市自身でさえ最終的な土地課題対策費の予測を立てることができていないと思われる。それにも関わらず、大阪市が本件借地権設定契約に伴い、土地所有者責任の合意を締結することは、著しく合理性に反している。
大阪市は土地課題対策の実施内容を直接管理できない立場にある
基本協定書では、カジノ事業地の地中障害物の撤去、土壌汚染対策及び液状化対策(土地課題対策」)をカジノ事業者自らが実施するものとなっている。土地所有者責任の合意では、大阪市は土地課題対策の実施内容を管理できる立場にはない。つまり、カジノ事業者が土地課題対策として支出したとする費用が、そのまま土地課題対策費として大阪市の負担となるおそれが強い。大阪市にとっては極めて不利な条件の契約を結ぶことは、著しく合理性に反している。
借地権設定契約及び土地所有者責任の合意は違法である
訴状では、違法性について次のように結論付けている。
「大阪港湾局長等が本件借地権設定契約に伴い締結される土地所有者責任の合意は、大阪市にとって著しく不利な条件で特定の民間業者に他に例のない便宜を供与する内容であり、かかる合意を含む本件借地権設定契約、またはかかる合意を締結すること及び土地課題対策費を支出することは、地方公営企業として行われる場合、その独立採算制等を潜脱し、これに抵触することになるので、これらの財務会計上の行為は、憲法14条、地方自治法2条、地方財政法4条1項、同法6条、地方公営企業法3条、同法17条の2第2項、大阪市港湾事業の設置等に関する条例2条、同3条等に違反しており、違法である。」
今回は、第1事件の請求内容の根拠として、何が違法となるかを原告の指摘についてみてきた。次回は、第2事件について見ていく予定だ。
ucoの活動をサポートしてください