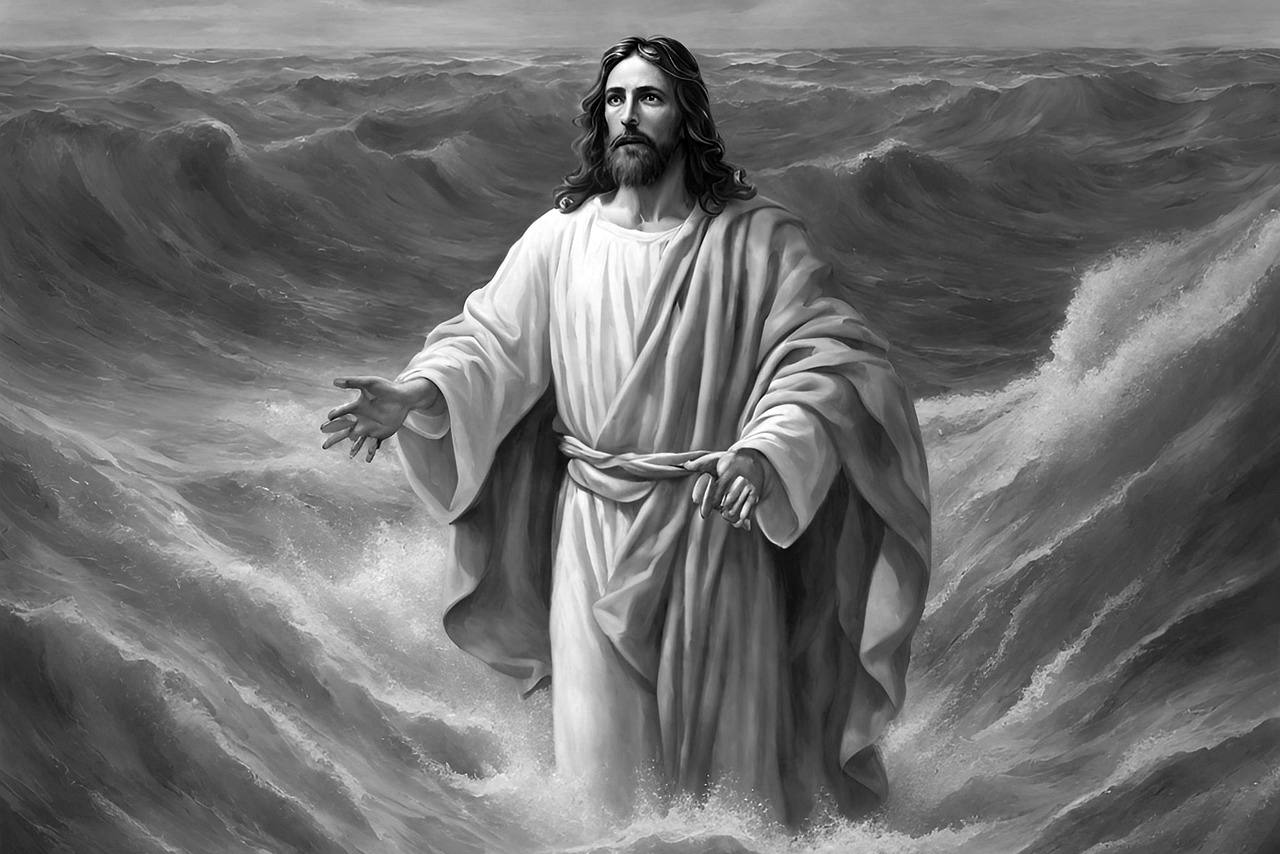最近の講演会での出来事。
先週末、東日本大震災をテーマにしたシンポジウムに参加した。
その際、震災から14余年が過ぎ、その過程での行政の方法の評価や現時点での暮らし方等、多岐にわたって議論された。
だがその際、国や行政の大きなしくみではなく、ただ困っている友人たちをなんとかしたい、それ以上のことはあまり興味がない、という方の取り組みが紹介された。
多くの方々が亡くなり、そのことで多くの方が苦しみ続けている。
それを制度とか大きなしくみ、そして自治でどう作り上げていくのかというマクロ的な解決法の議論が多かった中で、ミクロに一緒に助け合える人たちだけでまず組み立てていくことをやってきた方の話だった。
これには少しショックを受けた。
その根底にあるのは「万民思想」と「選民思想」なのではないか。
困っているすべての方々のためにか、
困っている中でも大きな意思を持つ方々のためになのか、
もちろん二者択一ではないのだが、視点の違いで随分見え方が異なる。
人は、なぜ自らの社会を自らで治めようとするのか。
自治の根底には「自分たちで決めたい」という願いがある。
しかし、その「自分たち」が何を指すのかによって、自治のかたちは大きく変わる。すべての人を含む「万民」なのか、能力や使命をもつ「選民」なのか。
この根本的な思想は、現代の自治を考えるときに押さえておかねばならないと感じて筆を執った。
万民思想――「すべての人が主権者」という希望
万民思想とは、あらゆる人が同じ価値をもつという考え方である。
人種・性別・身分の差を超えて、すべての人間に発言権と尊厳があるという信念が、その中核にある。
近代以降の民主主義、憲法、基本的人権、普選制度などは、この万民思想の上に築かれてきた。
自治において万民思想は、「誰もが社会の担い手である」という理念として現れる。
町会の会合で発言する市民、地域の課題を共有するボランティア、若者や外国人の意見を取り込もうとする行政――これらはいずれも、万民思想の実践である。
つまり自治とは、特別な人間だけでなく、日常の生活者が社会の構成者として意識を持つ営みなのだ。
しかし、万民思想が現実化する過程では常にジレンマが生まれる。
全員の意見を尊重しようとするあまり、決定が遅れ、責任が曖昧になる。
誰もが平等に語る社会では、誰も責任を取らない構造が生まれやすい。
理想の平等が、現実の無責任へと転じることがあるのだ。
私自身には、大前提は万民思想の元、自治が行われなければならないという呪縛にも似た気持ちがあった。だから、上記の点については「民主主義(万民思想)を成立させるためのコスト(リスク)なのだ」と言い聞かせてきた。

選民思想――「導く者の責任」と「支配の誘惑」
一方、選民思想は、社会の秩序と方向性を維持するためには「選ばれた少数」が必要だという考えである。
宗教的には「神に選ばれた民」、政治的には「指導的エリート」、文化的には「知識ある専門家」として現れる。
自治においては、地域のリーダーや行政の有識者がこの役割を担う。
方向を定め、責任を負い、他者を導く者がいなければ、共同体は動かない。
選民思想は、万民思想が生みやすい混沌を整理し、統合の力を与える。
しかし、この思想にももちろん危うさがある。
「選ばれた者」が自らの正しさを過信すれば、自治は独善・独裁へと変わる。
民意を「理解していない大衆」「アホな市民」とみなし、現場の声を切り捨てる。
やがてそれは、権威主義や官僚主義として固定化し、「自ら治める」という自治の精神すらも蝕んでいく。
そのため、ほとんどの自治を語る人々は、選民思想を危険視し、また恐れる。そういう大前提があるため、今回のシンポジウムでの発言には、非常に驚いた。
ふたつの思想をつなぐ「対話の場」

しかし本来、このふたつの思想は車輪の両輪ではないか。
万民思想は包摂を志し、選民思想は秩序を求める。
それぞれが必要な力を持つが、単独では自治を支えきれないであろう。
万民思想だけでは決断できず、選民思想だけでは閉じてしまう。
ゆえに、現代の自治には「これらをつなぐ場」が求められる。
それは、情報の公開だけでなく、熟議の文化を根づかせること。
住民が学び、理解し、納得した上で判断できるようなプロセスを設計すること。
自治とは「意思決定の場」であると同時に、「学びの場」と位置づけることができる。
対話を通じて万民思想の包摂を守り、選民思想の専門性を活かすことだ。
これらを循環させる構造ができたとき、自治は単なる制度を超えて「文化」となるではないか。
自治とは「成熟した民意」のかたち
万民思想が生み出した平等の理念は、人類の大きな進歩である。
だがそれを現実の自治に落とし込むには、選民思想がもつ「責任」と「判断」が必要である。
問題は、それらのいずれかに偏ることだ。
平等だけでは漂い、指導だけでは固まり、また単なる熱情だけでは燃え尽きる。
自治とは、これらのエネルギーを絶えず調整しながら進む「揺れる秩序」である。
真の自治とは、選ばれた者に任せることでも、大衆の声に従うことでもない。
「考える民」が「感じながら決める」プロセスそのものである。
そのとき初めて、自治は制度や組織を超え、生活と精神のレベルで息づく。
万民思想の理想を胸に、選民思想の責任を担い、情熱を持って使いこなす――
このバランス感覚にこそ、これからの自治の可能性があるのではないだろうか。
遠く東北の地で、そんな自治の未来を考えてみた。
<山口 達也>