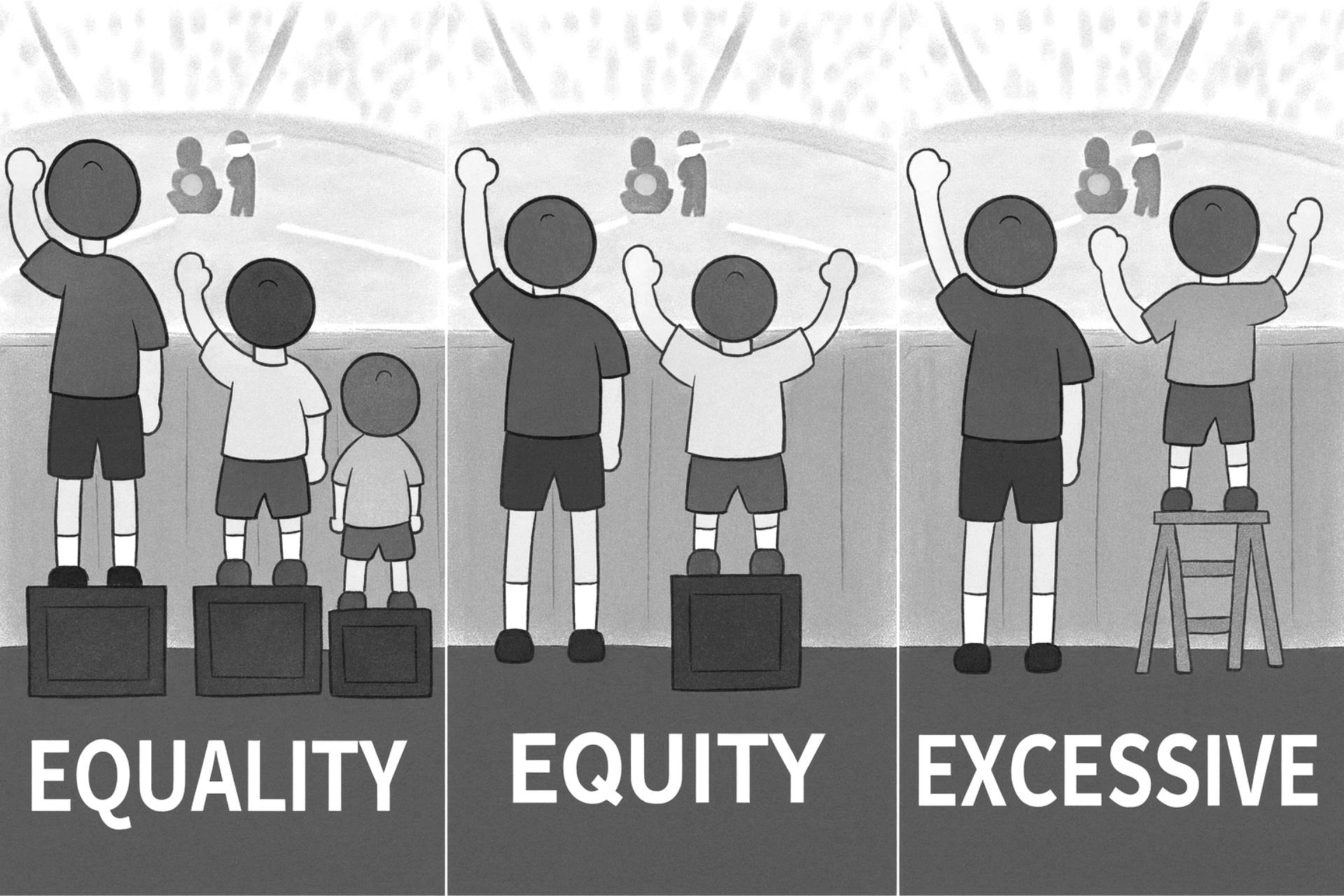日本はすでに人口減少・世帯縮小の長期トレンドに入り、住宅・都市インフラの総量拡大を前提とした再開発は制度疲労を起こしている。
近年の「拡大量」を維持する再開発の作法そのものを問い直し、維持管理と終末期(出口)まで見据えた都市政策への転換を提唱している一人に野澤千絵氏(明治大学)がいる。本稿は同氏の主たる論点を共有するものである。
人口減少なのにタワーマンションの理由
人口減少がこれからも続くという状況なのに、タワーマンションを組み込む再開発が続くのはなぜであろうか。
いくつかの要因があるが、人口減少だろうがなんだろうが、企業としてはずっと売上を立て利益を出し続けていかねばならない。
だからといって、これまでキーテナントとなっていた商業施設はネット通販やモータリゼーションによって、これまでの勢いはない。カフェや飲食店系のチェーン店舗がそのすべてを埋められるわけでもない。
とするとあとは住居で埋めていくしかない。そのためにはタワーマンションが最も簡単な解決方法なのである。
一方、行政としては、安定的に入る税金が固定資産税であり、人口減が確定している中、容積率緩和や事業スキームによって供給拡大に誘導し、自治体間の人口獲得競争になんとか勝ち残りたいという思惑がある。
東京都心でさえ、住宅購入年齢層の世帯数が頭打ちとなる予測が示される以上、大阪での、需要の将来像と合致しない増床は、将来の空室・管理不全リスクを内包することは間違いない。

作ったら終わりの制度設計からの脱却へ
現在まで国が推進してきた「立地適正化計画」は、評価指標の設計と検証が不可欠であるがそれが明快に行われてはいない。誘導区域に施設ができたか、撤退せず維持されているか等の結果検証を制度的に組み込まれていないのである。
作って終わりの計画から、成果で測る計画への転換が不可欠であるが、一寸先は闇であり、長期計画をタワーマンションによる増床拡大計画では、行き当たりばったりと言われても仕方あるまい。
日本の都市計画家やそれらに携わってきた組織は、バブル時代に全くコントロールの効かないまちづくりを体験してきている。バラ色の未来はことごとく廃墟と化し、大きな負の遺産となった。
バブル時の行政責任も重く、行政主導でまちづくりを行っていくメリットよりもリスクのほうが先に見えてしまうため、民間主導で行うことでその責任の一端を放棄しているようにも見える。
いずれにせよ、作ったら終わりのしくみから、再構築する必要がある。

次世代型の再開発?
人口減少で制度設計の見直しというが、商業施設ではなく、タワーマンションではなくどういったビジョンを描けばよいのだろうか。
ひとつの方向性としては、小さくコンパクトに運用しながら一点集中ではなくネットワーク型の都市構造を再開発を核に進めていくかであろう。
密度の経済や生活サービス維持を掲げる一方、縮退戦略と整合する投資に選択と集中を徹底し、低密区域のインフラ縮減や用途転換のための合意形成・補償設計を同時に進める必要がある。ビジョンを共有できずにすすめると理念倒れに終わる可能性も高い。
一言に縮退戦略というが、人類がまだ経験したことのない人口減少社会が間近に潜んでいる。
再開発という手法自体が実は次世代にはふさわしくないのかもしれない。もっと緩やかな無駄も無理もない新たな手法が求められているはずである。
ucoの掲げる、進化する自治は、この人口減少社会において非常に重要なキーワードのひとつであることは間違いない。
<山口達也>