津波避難ビルは“安全地帯”か、“孤島”か
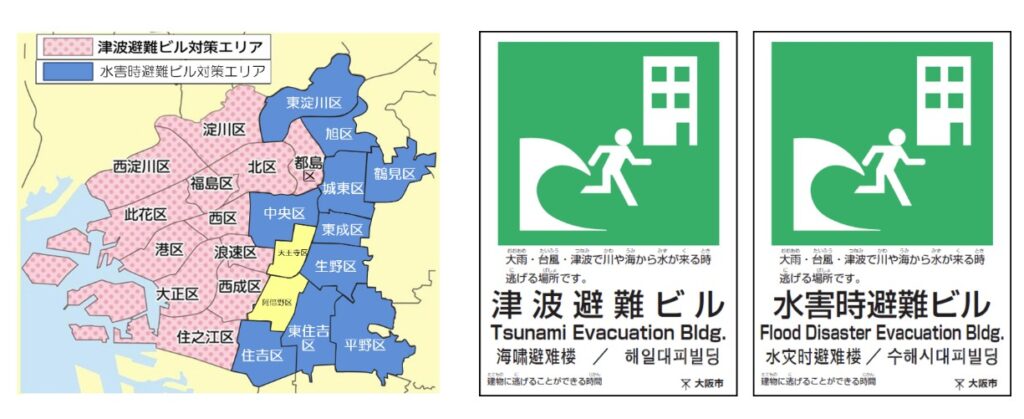
津波避難ビル。それは津波から身を守る「一時的な避難場所」として設定された建築物である。だが、そこに逃げ込んだあとのことについて、どれほどの人が考えたことがあるだろうか。避難ビルとは「逃げ場」であって、「暮らし場」ではない。言うなれば、災害時の“浮き輪”である。しかし、浮き輪に乗ったまま数日を過ごす人間など、本来はいない。
ましてやそのビルがマンションだったり、オフィスビルだったりすれば、管理権限や入館制限も存在する。避難所でありながら、受け入れる体制ができていない場所もある。「上に逃げれば安心」という言葉の裏には、“その先どうするのか”という問いが隠れているのだ。
避難はゴールではなくスタートである
防災訓練では「高いところへ逃げましょう」と教わる。しかし、津波は一過性ではない。第二波、第三波と続くことも多い。水が引いて、助かった…と思った瞬間から始まるのが、本当のサバイバルである。
例えば、エレベーターは使えない。階段を登ってたどり着いた最上階に、要配慮者がいた場合、そこで介助をどうするのか。ペットを抱えて避難してきた人はどうなるのか。逃げ込んだあと、すべてが解決するわけではない。
避難行動はプロローグに過ぎず、真の物語は「避難後」に始まるのである。
現場で起きた、ある“あるある”話
ある沿岸都市の実話である。訓練では毎年避難ビルとして指定されていたビルが、いざ本番の災害で施錠されており、誰も入れなかった。別の町では、ビルに逃げ込んだはいいが、住民同士が「ここは俺のオフィスだ!」「いや非常時なんだからいいだろう!」と押し問答を始め、最終的にみんな屋上に避難して無言になった。
このような「避難ビルあるある」は、実は全国各地で繰り返されている。避難とはドラマであり、予期せぬ人間模様の交差点なのだ。
トイレ、食料、情報…ライフラインの盲点
避難した先に、トイレが使えない。飲料水がない。電波が入らない。非常食が配られない。これは、想像力の欠如というよりも、避難ビルという制度設計そのものに“仮設性”があるからだ。
一時避難場所に過ぎないのだから、そこに備蓄や給水車はなくても当然――などという発想は、避難生活の現実を無視している。たとえ数時間でも、命を繋ぐインフラが必要である。
情報が入らず、SNSも使えず、家族とも連絡が取れない。そうした状況に備えて、各ビルに最低限の無線やラジオ、簡易トイレなどが配備されるだけで、避難後の安心感は大きく変わる。
行政はどこまで準備しているのか
地方自治体の中には、津波避難ビルに簡易トイレを常備しようという試みや、マンション管理組合と協定を結び、鍵の管理を緩やかにする動きもある。しかし、これはごく一部の先進例に過ぎない。
防災計画では、避難ビルの指定だけがなされていて、「その後の暮らし」については計画の枠外であることが多い。これでは「逃げろ」と言われて終わりだ。まちづくりの視点から言えば、避難とは自治の実践そのものであるはずなのに。
コミュニティの力が生死を分ける
最後は人である。誰が水を運んでくれるか。誰が要支援者のそばに寄り添うか。食料が足りなければ、誰とどう分け合うのか。答えは行政ではなく、コミュニティにある。
防災を制度や技術の話に留めることなく、「近くの誰と」「どんなふうに」乗り越えるかを、日常の中で話し合っておく必要がある。「逃げた先で出会う誰か」に思いを馳せることは、まちづくりの根幹でもある。
「避難のその先」を日常で描くために
避難ビルは“建物”である前に、“つながり”の象徴でもある。災害時だけでなく、平時からそのビルのことを知り、使い、管理者と話しておくことが、生死を分ける行動につながる。
一度、家族でそのビルに登ってみよう。トイレはどこか、電波は届くか、雨風はどうしのげるか。子どもが「なんか秘密基地みたい!」と言ってくれたら、それは立派な防災教育だ。
「避難してからが勝負」。このリアリズムは、自治とコミュニティの課題として避けて通るわけにはいかないだろう。
命が助かることが大前提ではあるが、熊本地震では、災害関連死のほうが圧倒的多数を占めている現状を踏まえ、UCOでは、自治とコミュニティという観点からこの問題を深めていきたい。



