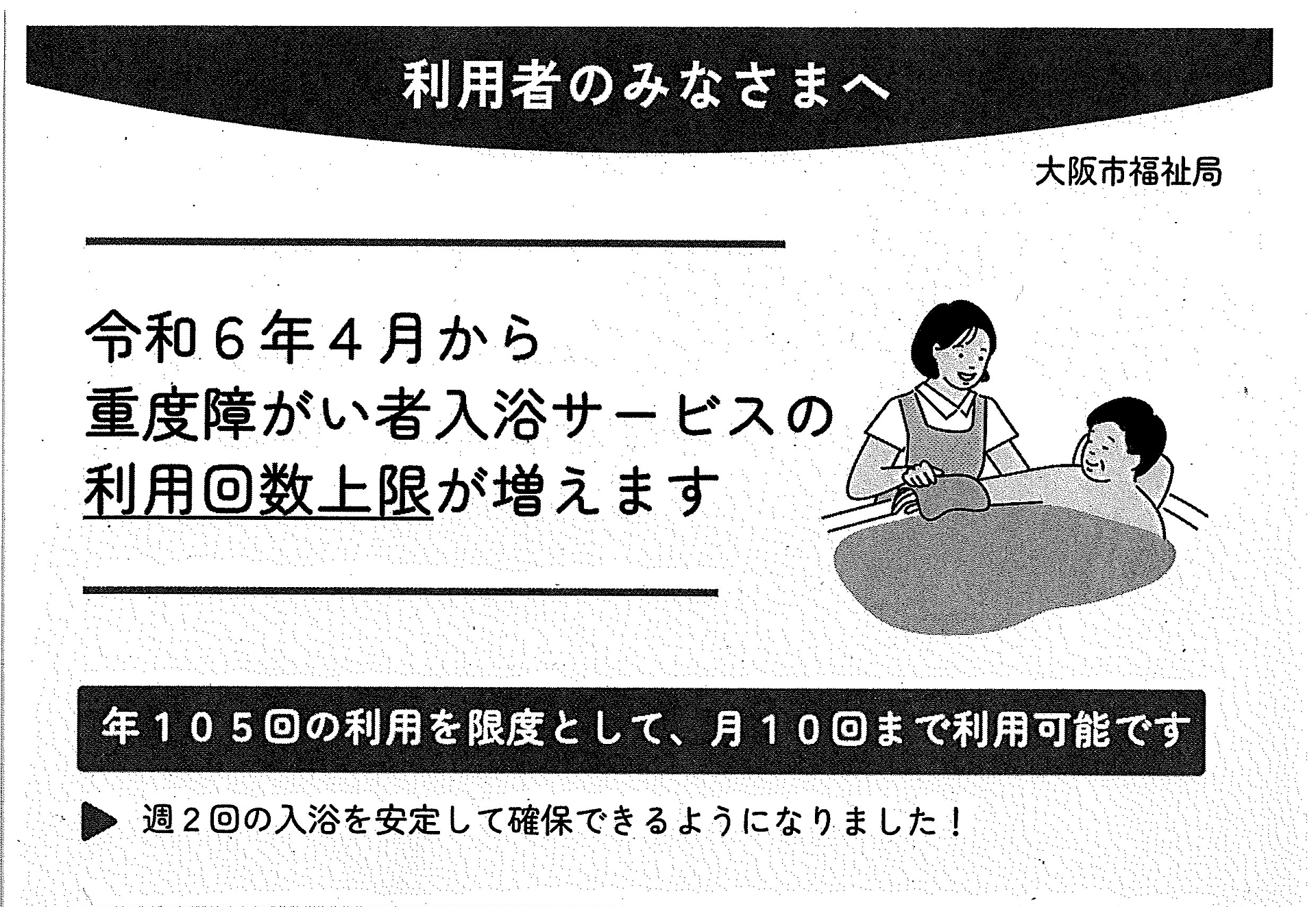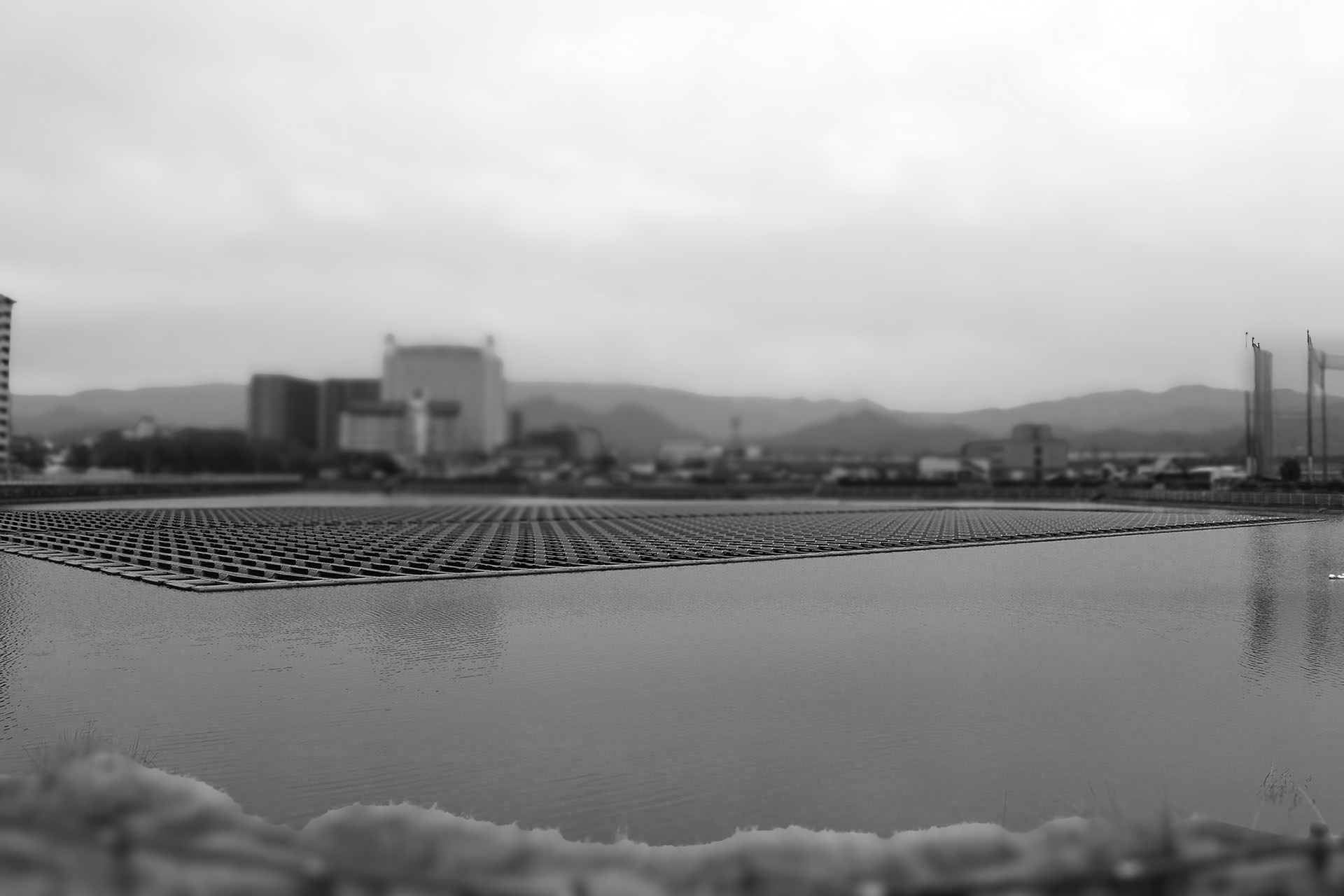いま一度、市民力を思い起こす
ucoは「進化する自治」を考え、実現するためのアプローチを模索している。
21世紀になっても続く「お上」行政に慣らされている市民
地域社会を構成する市民の多様性や、地域環境がもつそれぞれの事情や問題など、戦後連綿と続いてきた「大衆」を前提とした自治体運営や行政のあり方は、すでに時代にそぐわなくなってきている。
そのことは、自治体を運営する首長や行政官の中でも当然理解されているだろうし、あえて提言するようなことでもないとは思う。
しかし多くの行政運営は、首長をはじめ自治体内で企画され、計画が組まれ、市民は、すでに後戻りができないほど様ざまなことが決められ、決定事項として知らされるにすぎない。
明治・大正から昭和初期にかけ、大阪市は猛烈な勢いで発展し、工業と商業の中心地として隆盛を極めた。
莫大な予算で築いた大阪港周辺には他県から流入した多くの労働者が住まい、現在の港区周辺は人口爆発を起こした。港湾建設や物流の発展に伴い、港区には早い時期から市電が通った。それに伴い商店をはじめとして商業も活性化することで発展のスパイラルが生まれた。
工場建設により新たな人口流入や住宅地造成などを繰り返し、大阪市域は3度にわたって拡大されていく。これらはすべて行政による計画であり、それに伴い、上下水道、電気鉄道、市民病院など自治体による様ざまな公設事業が生まれていく。
この時代、「自治」という概念が市民に浸透していたというわけではないが、発展を遂げていく街に住まう中で「わが町」という意識が生まれていた。全国各地同じような状況だろうが、大阪も多くの市井の力で都市計画が進められている。
当時の大阪市は、税収難に苦しんでいた。当時の税収はほとんどを政府が占有しており、地方財政はどこも窮乏していた。家屋税をはじめとする種々の独立税や公営事業による収入を立てる一方、御堂筋や地下鉄、下水道などは受益者負担というかたちで周辺の住民が建設負担をしている。また、寄付や民間の土地区画整理、市政への支援というかたちで学校用地や鉄道敷設などに協力している。
ある意味行政からの強制というかたちではあるが、市の進める都市計画に対して多くの協力を行っている。一方で行政側も市民に協力を求めるための話し合いを進めるとともに、社会事業、保険事業、福祉事業などをも進めている。この時期には国内結一の市立による大阪商科大学が設置(1928[昭和3]年)され、教育にも力を入れていた。
自治体運営は行政と議会だけで成り立つか
特に大都市において一般市民の生活は、行政の力によるところが大きいが、行政任せ、あるいは行政の思惑だけで地域や生活の実態に沿った運営・運用は行えるだろうか。
大阪市阿倍野区では今年度(2025年)から2027年度までの3年間に取り組む「阿倍野区地域福祉計画」を発表している。阿倍野区保健福祉課長名による案内の中で次のように述べられている。
「第3期 阿倍野区地域福祉計画(案)」について、昨年1月にパブリックコメントを実施いたしました。パブコメではご意見はありませんでしたが、この間、区政会議や地域福祉推進会議等でご意見等をいただいた皆さま重ねてお礼申し上げます。
パブコメによる意見はなかったが、区の公式会議での意見は確認したので、計画案は正しいものとして扱う、ということでよいのか。なぜパブコメに意見が寄せられなかったのかは問わないのか。あるいは改善をするつもりはないのだろうか。この件に下記らず、パブコメの募集についてはネット上で告知されているだけで、区政広報や市政広報などで告知されることがほとんどない。注意を払ってサイトチェックをしていない限り、どういうパブコメが実施されているかはわからないことがほとんどだ。このような行政の態度で市民の意見を聞いたり、取り入れたり、あるいは市民協働が図られているといえるだろうか。
大阪市においては、地方都市に見られるような市民に歩み寄る姿勢は感じられないことが往々にしてある。
このような市政からの転換、新しい市民と行政の向き合い方として「進化する自治」の実現について考えていきたい。
vision50とは何か
いま、世界的な気候変動に対してエネルギー、農業生産、防災といった都市生活に重要な分野では、これにどのように対応していくかは、ある種死活問題と考えていい。
この分野については国主導を待つまでもなく、地方・地域による独自の対策や産業転換、エネルギーの自給自活用などを検討する時期に来ている。
しかし、現在の大阪市は、夢洲の開発事業をはじめとして開発一辺倒の土建政治を続けている。開発に関与する業種・事業者への利益配分に多くを割き、生活基盤への対応や医療・福祉や防災への十分な予算配分がされていない。
開発から生活防衛へ。都市計画はいま大転換を求められている。
ucoではvision50をベースに、様ざまな検討課題について発言していこうと管変えている。
ucoの活動をサポートしてください