ucoスタッフによる日頃の様々な問題意識を雑感としてお届けしています。
 コラム
コラム 「信任」という魔法と、私たちの沈黙と
騙すほうが悪いのか、騙される国民がダメなのか。Photo by Pixabay on Pexels.comこの問いは、怒りと無力感が混ざったときにふと口をついて出る言葉である。だが、その二項対立に乗った瞬間、思考は止まる。政治の側の欺瞞か、...
 コラム
コラム 学校が減る時代に、15年契約は合理的なのか
猛暑対策として進められる大阪市の小学校体育館エアコン整備。だが一方で、市は学校統廃合を前提とした配置見直しを進めている。学校減少時代に民間事業者が設計から維持管理までを一体的に担う長期契約は、将来の変化を見通しての政策か?
 コラム
コラム ホワイト社会と「批判なき選挙」の違和感
4今回の衆議院選挙を眺めながら、どうにも言語化しづらい違和感が胸に残っている。いくつもの政党が、あまりに強引で荒っぽい手法をとる高市首相をディスり、攻撃し、批判した。だが、その批判は広がるどころか、どこか空転しているように見えた。むしろ逆効...
 コラム
コラム 唐突な大阪市「水道管路更新40年前倒し」発表のなぜいま?
遅々として進まなかったインフラ行政と国の方針転換先週金曜日(2026年2月13日)、大阪市は突然「使用可能年数を超過した管路の更新を約40年前倒しします」と発表した。これまで入札不調(1社も応募が無い)や使用可能年数を超過した管路解消まで約...
 コラム
コラム 「統率」という思想
なぜ今、強いヒエラルキーが支持されるのか会社経営のセミナーって、かつては「地獄の3日間研修」から始まり、あやしそうな「マインドコントロール的研修」まで様々なものが大手を振ってきた。かくゆう私もいろんなセミナーに参加してきたが、今日は最近参加...
 コラム
コラム 大阪市の民泊事情と、終わりそうにない民泊トラブル
特区民泊の申請受付停止を発表後も申請数は増加の一途昨年、大阪府下で運営されている民泊で近隣住民とのトラブルや大阪府・大阪市への苦情が相次ぎ、報道でもクローズアップされた「民泊問題」。大阪市は、昨年11月28日付で「特区民泊」の申請受付を当面...
 コラム
コラム 2026年という分水嶺―「次の景色」俯瞰
敗戦の1945年以降の日本史を大きく俯瞰すると、いくつかの明確な節目が浮かび上がる。戦後復興、高度経済成長、第一次・第二次オイルショック、バブル経済、1991年のそのバブル崩壊、そして「失われた30年」。さらに2020年代初頭のコロナ禍は、...
 コラム
コラム 医療機関の赤字・倒産が招く医療空白地帯の課題
全国レベルで続く医療機関の赤字化近年、「病院の赤字」「医療機関の倒産・休廃業」がテレビやニュースで繰り返し報じられている。背景には物価高・人件費増、医療人材確保の困難、診療報酬とのギャップなど複合的要因がある。視点を利用者側に移すと、単に“...
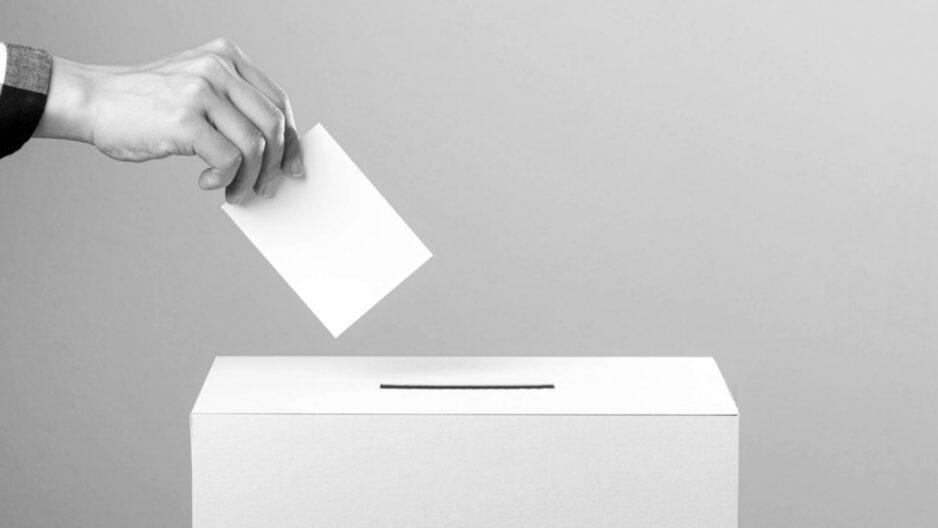 コラム
コラム 選挙悪用への抗議―市民の投票=「白票」
不毛な首長選をこえる――市民はどう投票すべきか突然の衆議院選挙に便乗して、全く意味を持たない不毛な大阪府知事・大阪市長選挙が行われようとしている。大阪府知事・大阪市長選という首長選挙は、その選挙制度の悪用であり、もう単なる再選挙の域を超えて...
 コラム
コラム 県知事発言「外国籍職員採用停止の検討」が呼ぶ波紋
2025年12月25日の定例記者会見で、三重県の一見勝之知事は、県職員採用における「国籍要件」を復活させ、外国籍職員の採用を取りやめる方向で検討していることを明らかにした。この発言は、複数の報道を通じて国内外に伝えられ、行政判断の妥当性や人権・地域共生の観点から議論を呼んでいる。
