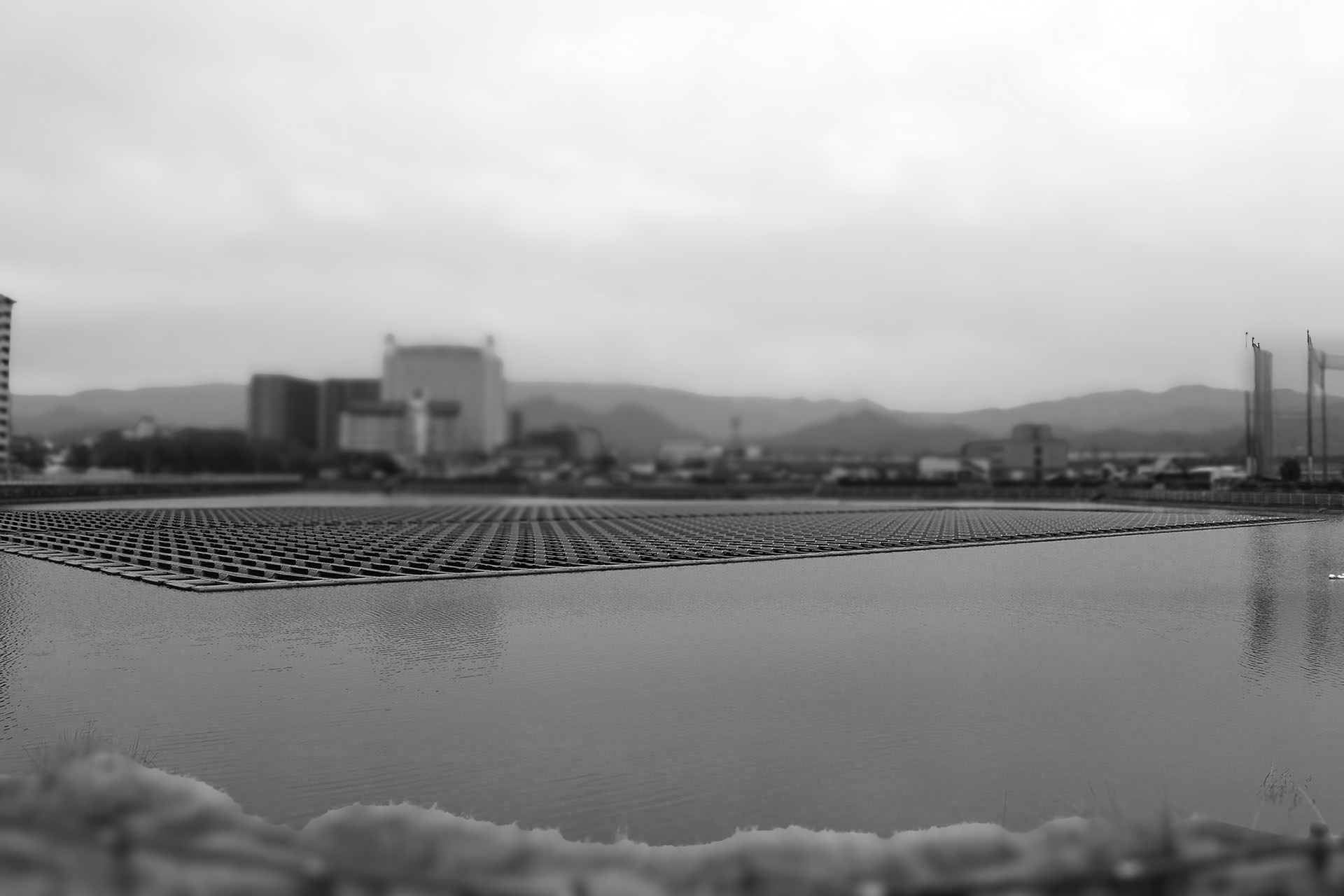はじめに:「共創」の時代へ
防災の現場で何度も突き当たる壁は、「誰が担うのか」である。行政だけでは動かない。市民だけでも限界がある。企業は利益を求めるし、福祉や教育機関は専門外とされることもある。
しかし、いま必要なのはそれぞれの立場の違いを超え、目的を共有し、「ともに創る」ことである。共創——co-creationという概念は、防災と自治を結び直すキーワードである。単なる連携ではなく、対話と相互理解、そして役割の越境によって、新しい自治の構造が形づくられていく。
この最終回では、「共創」という視点から、防災を再考し、地域自治の新しいかたちを描き出す。
行政は万能ではない——だからこそ共創へ
災害対応の基本は「公助」にある。確かに消防、警察、自衛隊といった公的機関の存在なくして、大規模災害への対処は困難である。しかし、その対応には限界がある。
例えば、発災直後の72時間以内にすべての被災者に救助の手が届くわけではない。道路が寸断され、孤立する地域が生まれる。物資が届くまでに数日を要する。その間、生き延びるのは「自助」と「共助」の力にかかっている。
行政は制度と予算を持つが、地域の細やかな事情までは把握できない。だからこそ、「住民との共創」によって制度を現場につなぎ、制度を「運用可能な現実」へと変える必要がある。
市民は「受け手」ではない——参加と意思決定の主語へ
多くの住民は、災害が起きたときに「行政が何とかしてくれる」と考えがちである。しかしその考えが、支援の遅れや混乱を招くことは過去の震災で何度も証明されてきた。
市民は被害者であると同時に「支援の主体者」である。平常時から地域の課題を共有し、防災の取り組みに参画することこそが、真の自治である。
避難所運営委員、町内の防災リーダー、情報連絡員、炊き出しチームなど、市民が「自らの居場所」を見出せる仕組みが必要だ。行政に対する「要望」ではなく、「提案」として自分たちのまちを創っていく。その主体性が、共創の第一歩となる。
企業と防災——営利と公益の交差点
災害時、地元の中小企業や商店は、物資の供給や物流、施設の提供などで極めて重要な役割を果たす。阪神・淡路大震災でも、電気が止まりスーパーが閉店するなか、地元の八百屋が店を開けて食料を分け合ったという話が残っている。
一方で、企業にとって防災は「コスト」でもある。だからこそ、CSR(企業の社会的責任)やBCP(事業継続計画)といった枠組みを超えて、「地域の一員としてどう貢献できるか」という視点が問われる。
例えば、コンビニと自治体が協定を結び、災害時には水と食料を優先供給する。また、物流会社が高台への物資輸送を担うなど、企業のノウハウを地域防災に活かす試みが全国で広がっている。
防災は公共だけの責務ではない。企業の持つ資源と知見を活用し、地域の中で役割を持つ。それが共創型自治の一つのかたちである。
福祉と教育を巻き込む「防災の横断化」
災害において最も困難なのは、要配慮者への対応である。高齢者、障がい者、ひとり親家庭、外国人など、災害弱者への支援は、日常的な福祉の延長でなければ成立しない。
つまり、福祉と防災は切り離して考えることができない。ケアマネジャー、民生委員、保育士、学校教員、介護事業者などが防災計画の中にどう組み込まれるかが、実効性を左右する。
教育現場においても同様だ。防災教育は単なる知識の習得ではなく、「自分で判断する力」「人と協力する力」を育むプロセスである。子どもが家庭に防災意識を持ち帰り、親を動かすような「世代を超えた共創」が、未来の地域を支える力になる。
共創の場をどう作るか——対話とルールの設計
防災共創のためには、行政、住民、企業、福祉、教育、それぞれの立場が顔を合わせ、対話する「場」が不可欠である。これが単なる情報提供や協議会ではなく、ルールを「ともに作る」ことに意味がある。
世田谷区などで試みられている「ラウンドテーブル方式」は、こうした共創のモデルとなる。参加者が肩書を外し、フラットな立場で地域の課題を話し合う。そして「できること」「できないこと」を持ち寄り、役割分担を明文化する。
このプロセスは、時間がかかる。面倒である。しかし、この対話の積み重ねこそが、有事において「自分たちのまちを自分たちで守る」という自治の基盤となる。
共創型自治の未来へ——防災は社会を変えるレンズである
防災は単なるリスク管理の話ではない。それは、地域社会の脆弱さをあぶり出し、持続可能な共同体の条件を問い直すレンズでもある。
少子高齢化、都市の孤立化、地域資源の枯渇、行政サービスの限界。こうした構造的問題に対して、「防災」を切り口に共創のネットワークを広げることで、新しい社会モデルが見えてくる。
住民が動き、企業が支え、行政が調整し、教育が育み、福祉がつなぐ。災害を前提としながらも、それを超えて日常を豊かにするための共創型自治へ。これが「防災の観点から自治を再構成する」というビジョンの核心である。
総まとめ:「防災×自治」再構成の4つの柱
最後に、本シリーズで論じてきた4つの柱を簡潔に整理する。
- 第1回:災害の経験から出発する自治の再構成
→ 熊本地震、津波避難ビル、防災士の事例を通じて、災害対応力の地域差を考察。 - 第2回:避難所とコミュニティ
→ 避難所の現実から、自治の構造が試される場面を検証。 - 第3回:情報共有の構築
→ 情報が届かない場所は命が危うくなる。自治単位での情報網整備の必要性。 - 第4回:共創による自治の未来
→ 多主体の参加による新しい自治像の提起。防災を通じて見えてくる社会構造の転換。
まとめ:災害を恐れるのではなく、備えの中で「つながり」を育てる
私たちはこれからも災害の脅威にさらされる。しかし、災害をただ恐れ、受け身になるだけではない。そこから「どう生き延びるか」「誰と生きるか」「どこで支え合うか」を考え、備えることができる。
防災とは、結局のところ「人間の共同体をどう保つか」という根源的な問いである。自治の再構成=進化する自治とは、その問いに答え続ける営みと読み替えることができるであろう。
ucoでは、ここまでの内容を具体的に実現するためのアクションを今後も配信予定です。