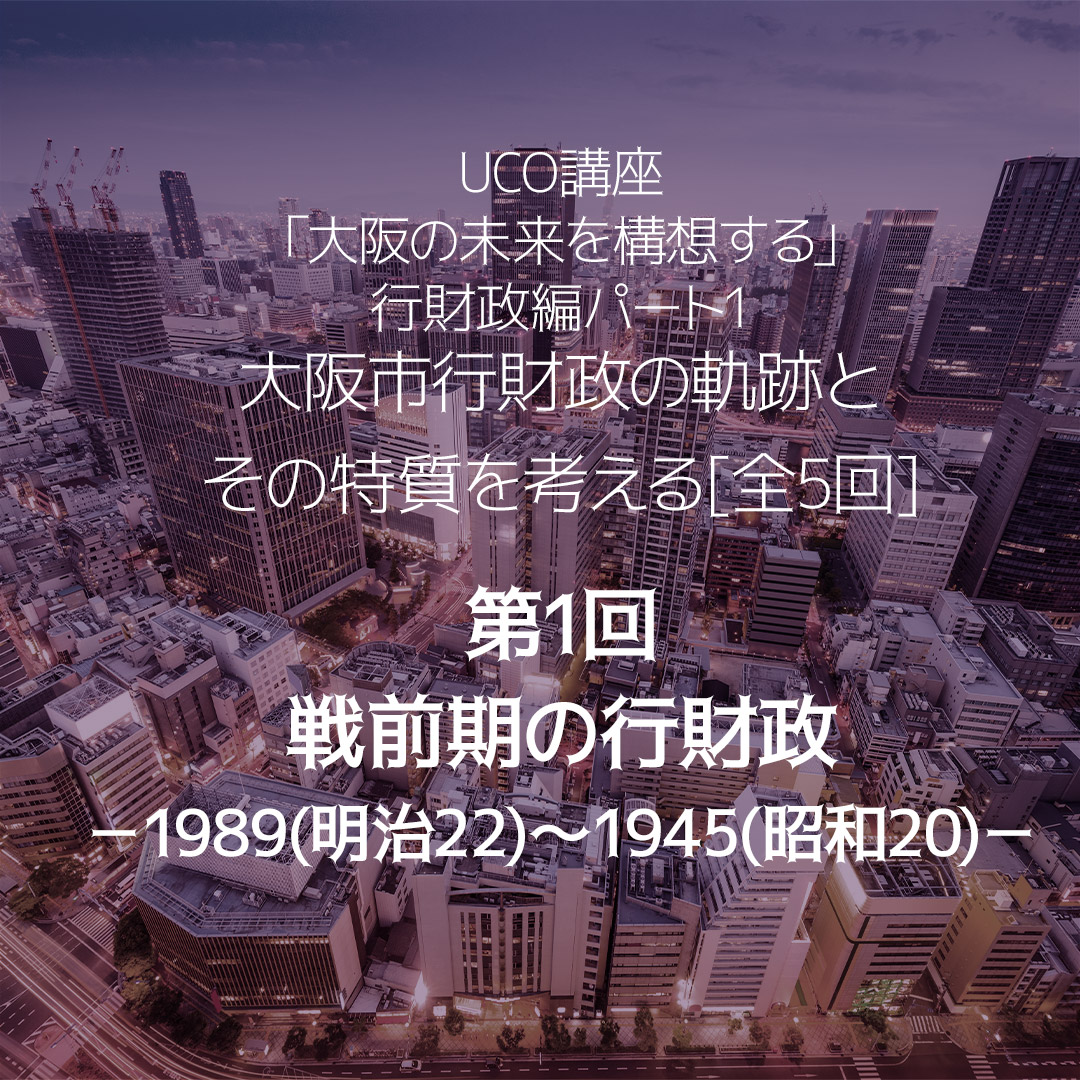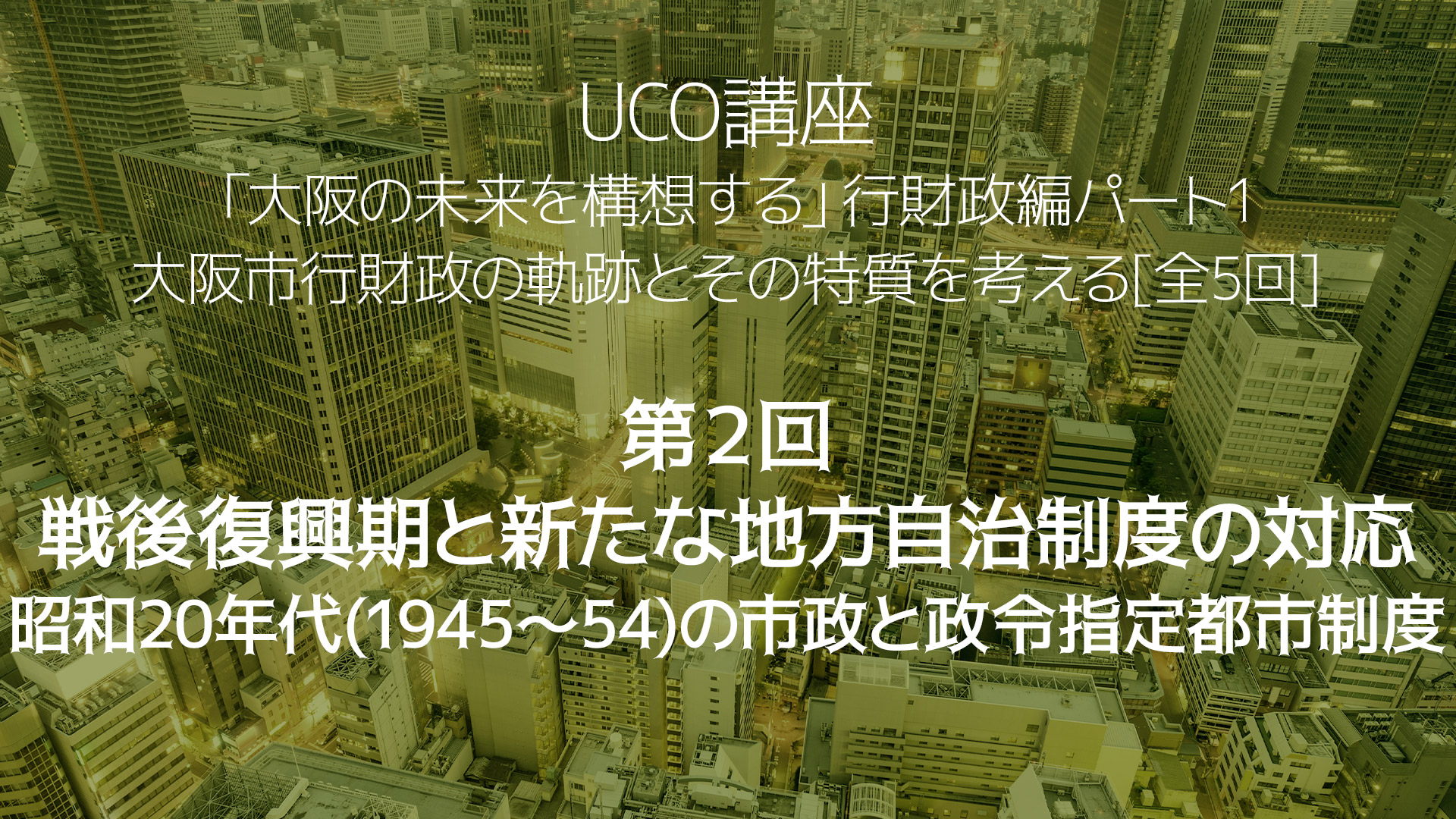大阪市を形作ってきた歴史を、その土地の成り立ちと経済、文化など様々な要素を持った「区」から見つめ直そうという試みです。
幕末の大阪の中心地であった「大坂三郷」を基礎としながらも、3つではなく「北区」・「東区」・「南区」・「西区」の4つの区から始まり、近代化や戦後復興、人口爆発を経て現在の24区となった経過をたどります。
区にはそれぞれ成り立ちの理由があります。特に大阪では商業が発達し、産業ごとに町を形成していったという歴史と文化があります。
そしてその土地の特性や、発展していった生業、育った産業など、地域を形作っていった要素は様々です。吸収して大きくなった理由や、大きくなって分区した時の経緯など、それぞれの「区」特有の、あるいは固有のワケがあることが多いです。
いま大阪市には、未来を展望する経済政策は無きに等しい状況です。政治的思惑による「カジノ=博打」を誘致する以外、何ら明確な経済的ビジョンや産業育成といった政策はありません。スローガンだけで実態とはかけ離れた「国際金融都市」を叫んだり、さまざまな問題が指摘されている「スマートシティ構想」といった夢物語ではなく、地に足の着いた産業のあり方を地域から見直すきっかけの一つとして、区の歴史から再構築してみます。
今回は、「150年の大阪の区の歩み」というテーマを考えています。
近年話題になりながらも、その成り立ちを語られる機会が少なかった大阪の「区」、大阪24区の足跡、歴史というものを一般の読者向けに書いた初めての本です。
その内容を動画でさらにわかりやすく、コンパクトにまとめてご紹介します。
明治生まれの最初の4区が現在の24区になるまでの足跡をまとめました。なぜこんなにたくさんの「区」ができたのか、それぞれの「区」はどんな役割を担ってきたのか、暮らしに身近なのに知られていなかった「区」。その誕生から現在までの大阪150年のドラマを私といっしょに思い描いていただければうれしいです。
ポイントは次の3つです。
まず、明治時代にできた最初の4つの区は、江戸時代の大坂三郷プラス1、この「プラス1」が第1のポイントです。
第2のポイントが、大正から昭和にかけて大阪が人口爆発した時代。それによって区が増える増区、区が分かれる分区が4段階で進みました。これを私は「4つのジャンプ(増区・分区の4段跳び時代)」と呼んでいます。
3番目のポイントは、平成に入って初めて区が減りました。区が減った「減区」、区が合わさって減った「合区」、これが時代の大きなターニングポイントでした。
この講座アーカイブを購入する