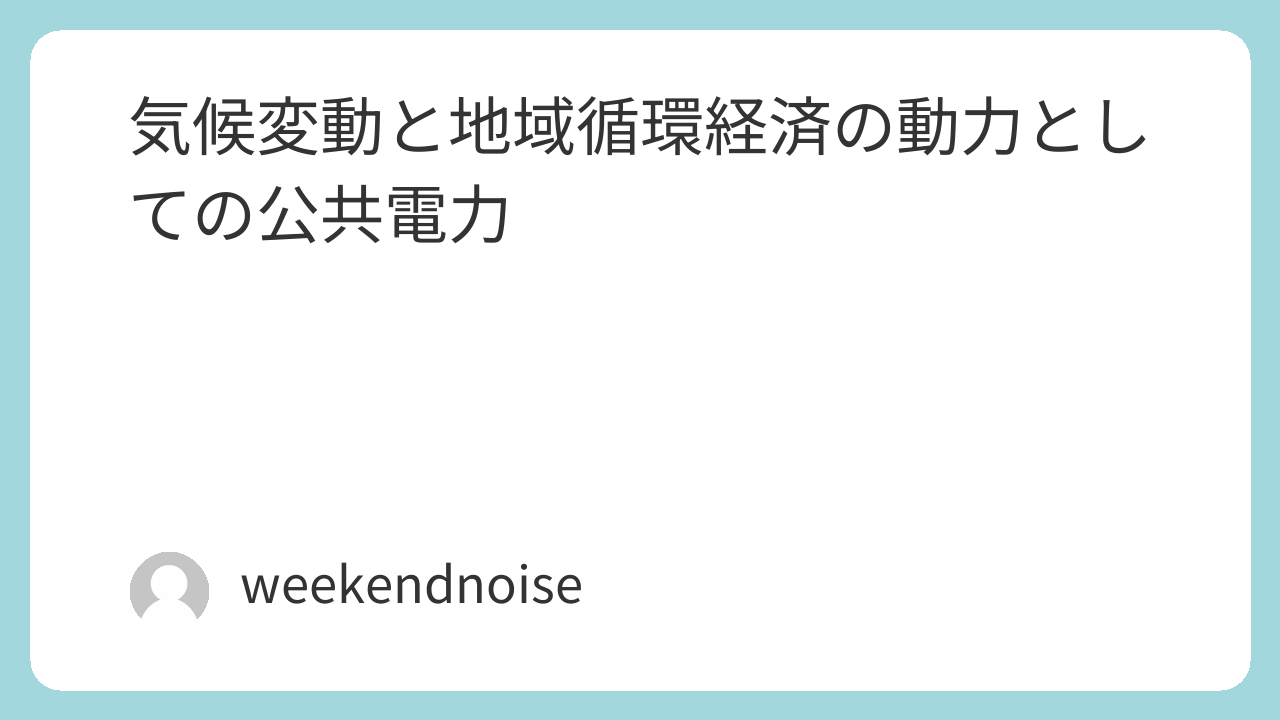気候変動と地域循環経済の動力としての公共電力
エネルギーから地域と自治を進化させる
地球温暖化や気候変動が、実際の気象の変化で体感できるようになってきた。極端な酷暑や渇水、国内やアジアをはじめ世界各地が洪水被害が頻発に起こっているなど、自然災害による被害の大きさも極端に大きくなっている。
その一方で、再生エネルギーへの転換や温暖化ガスの排出制限、またESG投資※や持続可能性を持った産業や経済への転換の動きは遅々としており、進んでいるようには見えない。
大阪市は、2022年10月に策定された「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕(改定計画)」において、「2050年 ゼロカーボン おおさか」の姿を描いて見せてはいるが、啓発事業や体験学習などが多く、実現に向けた具体的な動きは緩慢だ。
ucoは、「持続的社会を形成する文化都市=大阪」というスローガンをもって、具体的に自治体はどのような転換が必要かを考えた。そこで4つのコアテーマをもとに地域の抱える行政課題についてその糸口を見つけたい。
気候変動から派生する課題は多岐に及ぶが、生活に直結する課題として「エネルギー」「防災」「食糧危機」が思い浮かぶだろう。
エネルギー需要の増大は、電気代となってそのまま地域経済に影響を及ぼす。化石燃料を使い続けることは、地域の富が海外に流出していくことにもつながる。洪水や高潮被害に対する防災対策は十分に行われているか。また昨年来のコメ不足による高騰はもちろん、野菜の高騰や沿岸漁業の不良なども頻繁に起こっている。
vision50は、4つのコアテーマを進化する自治の一つの考え方として掲げ、日にちの生活や身近な経済の視点から、どのようなことが具体的に可能なのかを学び、探っていくシリーズです。
2000年以降の電力自由化の流れに始まり、国内の複数の自治体で「自治体新電力」が設立された。地域内で発電された電力を地域内の公共施設や民間事業所、一般家庭などに供給する小売電気事業者の中でも、自治体が出資者となっている事業者が「自治体新電力」と呼ばれている。
泉佐野電力は、関西では比較的早い時期にスタート。2015年4月から公共施設(当初34施設)への電力供給を始めている。これが西日本初である。