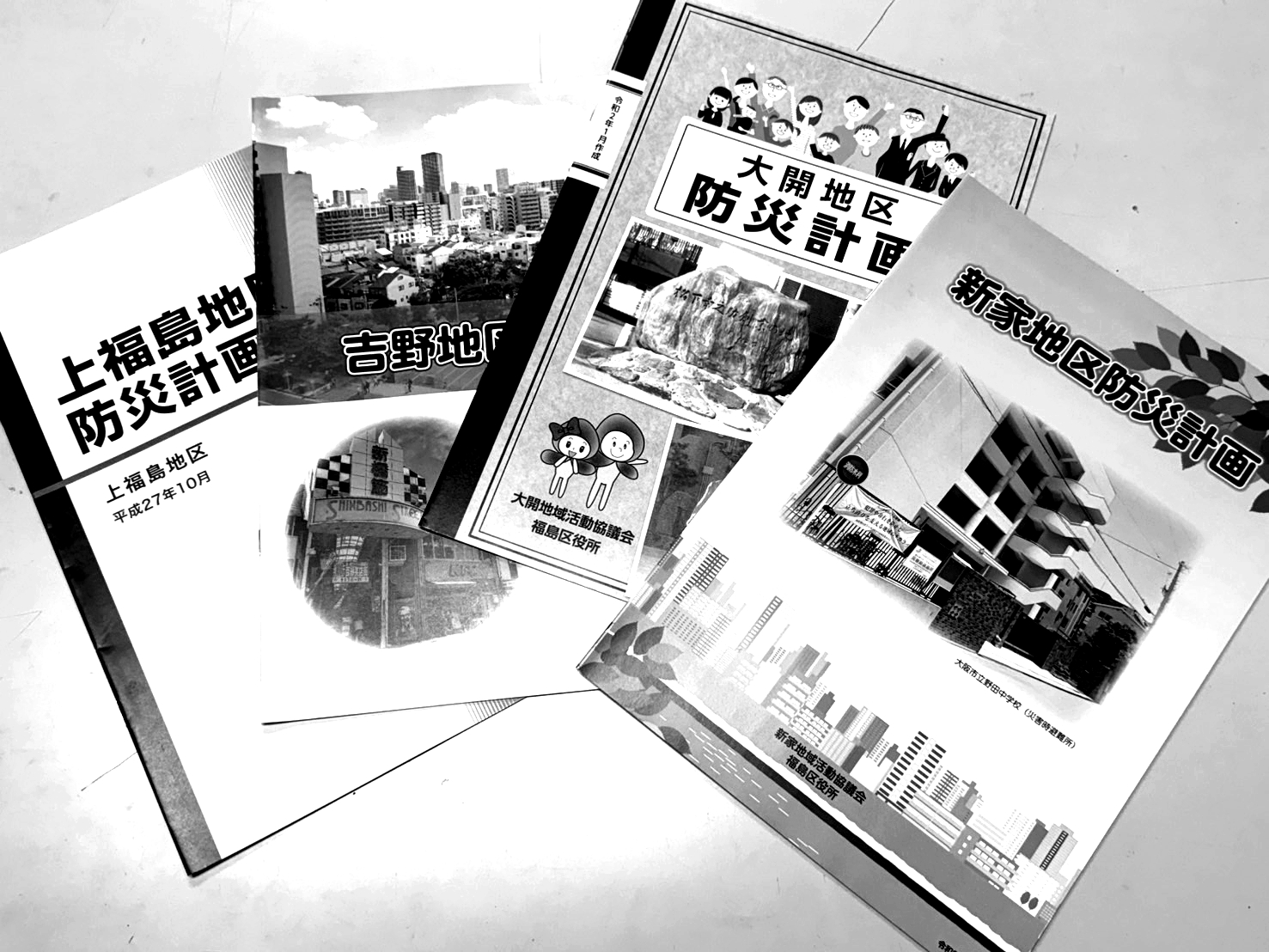空き家バンクはなぜ機能しないのか?
空き家バンクという言葉には、どこか希望が宿っている。使われなくなった住宅が、新たな住まい手のもとで再び息を吹き返す——そんな未来が描かれている。しかし、現実はどうか。とくに大阪市のような都市部では、その理想がことごとく壁にぶつかっている。
本来、空き家バンクは、自治体が空き家の所有者と住みたい人をつなげる「公的マッチングサイト」として機能するはずである。だが、実際の登録物件数は少なく、更新頻度も低い。そもそも所有者側が積極的に登録したがらないのだ。
行政は「登録してください」と呼びかけるが、所有者からは「誰が使うのか分からない」「売れる見込みがないのに公開したくない」「手続きが面倒」といった声が挙がる。この時点で理想と現実のミゾはかなり深い。
大阪版の「見せかけのマッチング」と行政のジレンマ
大阪版の空き家バンクを見てみると、都市部にも関わらず物件数はごくわずかだ。しかも、大阪市はゼロ。そして実際に内見ができる物件はさらに限られる。検索しても「商談中」「調整中」の表示。まるでフリマアプリで“売れてる風”を演出しているかのようである。
http://bank.osaka-sumai-refo.com/
一方で行政には「制度として用意した」というアリバイがある。「空き家対策しています」と言えるし、予算も使える。だが、この制度設計は市民の生活実感とはかけ離れている。要するに、制度はあるが、使えるようにはなっていない。
都市部では、不動産会社を通じた売却や賃貸のほうが手っ取り早いと考える所有者も多い。空き家バンクに載せることで「格安で買い叩かれるのではないか」という警戒心も働く。制度の外にある現実は、行政の机上の設計では捉えきれないのだ。
住民が使いにくい本当の理由とは?
空き家バンクが機能しない背景には、利用者視点の欠如がある。まず、物件情報が古い。掲載日すら書いていない。また、写真が少なく、間取り図もない、というケースが多い。想像してみてほしい。「誰かの親戚の家の情報を口頭で聞いた」ような感覚で、引っ越し先を決められるだろうか。
さらに、内見や契約の調整が煩雑で、担当者によって対応も異なる。ITに不慣れな高齢者にとっては、「まず電話して、そこから現地確認の調整を…」という流れだけでもハードルが高い。若い世代にとっても、LINEもメールも使えない窓口では不安しか残らない。
つまり、空き家バンクが機能しないのは「やる気がない」のではなく、「使いにくいから使われない」のである。そこに気づかなければ、どれだけ制度を整えても、住民は動かない。
売れない家、貸せない土地――制度の外にある本質
制度の盲点は、空き家の“物件としての魅力”以前に、「法的・心理的な障害」があることだ。たとえば、相続登記が未了で誰の名義かも分からない物件。あるいは、親が施設に入ってから放置され、空き家にしておくしかない家。登記や相続の費用をかけてまで売る意味がないと判断されるケースも多い。
また「貸すのが怖い」という声も多い。大阪市内でも、過去に“住んだ人が家賃を払わず出ていかない”といったトラブルがあった。そうした経験談が地域で語り継がれ、誰も貸そうとしなくなる。
つまり、制度外の「心理的壁」や「法律的ボトルネック」が、空き家の流通を止めている。空き家バンクはその上澄みしか扱っておらず、最も困っている人や制度を必要としている人の手前で止まってしまっている。
動かすのは「仕組み」より「人」かもしれない
空き家バンクが今後、地域の力として再生するためには、「自治」が鍵となる。たとえば、地域のNPOが所有者と丁寧に対話し、不安を解消しながら情報を整理する。あるいは、移住希望者とのマッチングをサポートする「地域の案内人」が入る。
制度の手前にいる人たちをどうすくい取るか。それは、行政の枠組みでは難しい。だが、自治の力、つまり地域の人間関係や信頼のネットワークならできるかもしれない。
空き家バンクを生かすには、まず「制度を整備する」ではなく、「制度の外で何が起きているのか」を見つめることが必要だ。空き家問題は単なる住宅流通ではない。人と人の関係の中で、まちの未来を問うているのである。
だが残念なことに、現在の大阪市政は、単に「民間でできるものは民間で」「身を切る改革」と称し、NPOと連携して住民のための仕組みを作っていこうという意志も予算もなく、人も配置していないのが実態だ。
ucoではこの空家問題から「進化する自治」の断片を拾い上げようとしている。