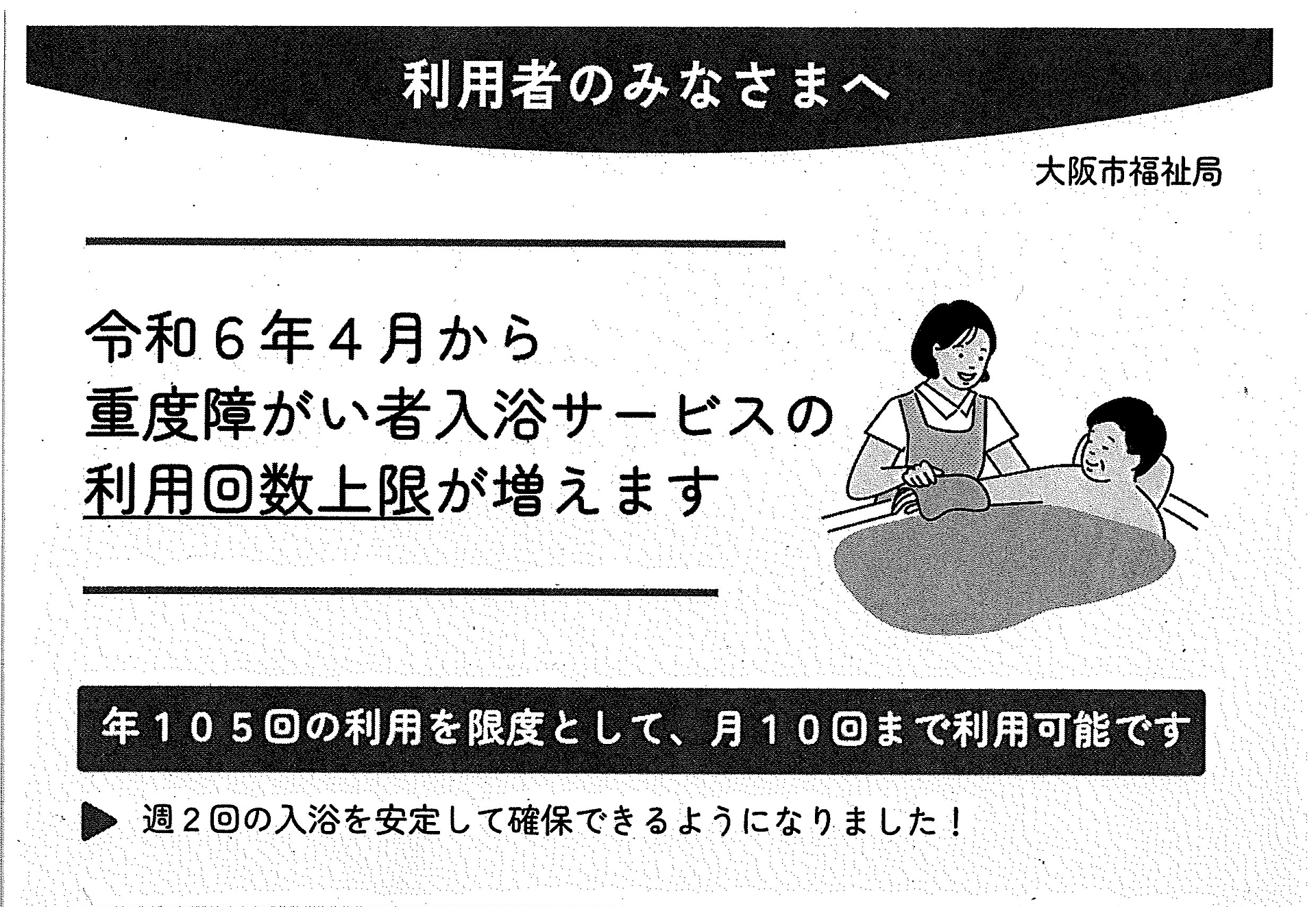このコラムは、東洋経済オンラインの「こども食堂から一線を引く」が良い記事だったのでそれを参考に再構成したものです。「こども食堂から一線を引く」 《こども食堂》の名付け親が決意した背景
記事で刺さった言葉
「地域力、居場所作りといいますが、そんな生やさしいものではないです。そういうことを行政の方も知ってほしい。あなたたちはお仕事ですが、私たちはボランティアだということを忘れないでほしい。こども食堂は行政の下請けではありません。(中略)また、地域には町会や商店会など既存の団体があります。自治会長や保護司、民生委員など、肩書きがある方たちもいる。こども食堂は地域の新参者で、なかなか関係を作りにくい。日本の体制って、国民をタダ働きさせるようにできているのではないかと思うこともあります。国民の善意を利用して、これはいいことですから、みんなで頑張ってください。頑張りましょうと。あおってきたんだなと私は思います。」(記事から引用)
行政と住民自治との隙間
ボランティア抜きに住民自治は成り立たない。本来は、行政と住民自治は対等で共にまちを作り上げていくしくみであるはずである。地域活動の最前線におられたこども食堂の近藤さんの決断(後述)は重い。
肩肘張らず、しかし着実に地域とともに生きるというしくみ自体の再構築が問われており、まさに新しい自治のあり方に一石投じていると感じた。
具体的には以下の要約を読んでいただきたい。(東洋経済の記事のリンク切れがあるかもしれないので要約を掲載したが、本記事をできるだけ読んで下さい)
こども食堂の名付け親・近藤博子さんの決断
近年、日本各地で「こども食堂」が急増し、その数は1万カ所を超えるに至った。地域のボランティアや団体が運営し、子どもたちに無料または低額で食事を提供する場として、多くの家庭にとって重要な存在となっている。その活動は、子どもの貧困対策や地域コミュニティの活性化に寄与し、社会的にも高く評価されてきた。
「こども食堂」という名称を広めた立役者であり、東京都大田区で「だんだん こども食堂」を運営してきた近藤博子さんは、2025年春、「こども食堂の大きな流れからは、一線を引く」との決断を公表した。13年間にわたり活動を続けてきた彼女のこの決断は、多くの関係者に衝撃を与えた。
近藤さんは、こども食堂が「良いこと」として広く認知される一方で、月に数回の食事提供や数キロの米の配布では、子どもの貧困問題の根本的な解決には至らないと指摘する。彼女は、子どもの貧困は、親の就労問題や教育、住宅など、複合的な要因が絡んでおり、国や自治体が真剣に取り組まなければ解決しないと訴えている。
ボランティア支援の限界と制度の壁
こども食堂の多くは、地域の善意とボランティアによって支えられている。しかし、近藤さんは、ボランティアによる支援には限界があると感じている。彼女は、こども食堂が「子どもの貧困対策」として過度に期待されることで、行政の責任が曖昧になり、制度的な支援の強化が後回しにされる危険性を指摘している。
また、企業がこども食堂に寄付をすることで、社会貢献のイメージを得る一方で、実際の子どもの生活状況は改善されていない現実もある。近藤さんは、こうした現状に対し、ボランティア活動だけではなく、制度的な支援の必要性を強く訴えている。
自治による持続可能な支援体制の構築
近藤さんの決断は、地域社会が抱える課題を、地域住民自身が主体的に考え、解決していく「自治」の重要性を再認識させるものである。こども食堂の活動を通じて見えてきた課題を、地域全体で共有し、持続可能な支援体制を構築することが求められている。
例えば、地域の企業や団体、行政が連携し、子どもたちの生活支援や教育支援を行う仕組みを整えることが考えられる。また、地域住民が主体となって、子どもたちの居場所づくりや相談支援を行うことで、よりきめ細やかな支援が可能となる。
こども食堂の活動は、地域社会のつながりを再構築するきっかけとなった。
しかし、今後は、ボランティア活動だけに頼るのではなく、地域全体で課題を共有し、制度的な支援を強化することが求められる。近藤さんの決断は、地域社会が自らの課題を自らの手で解決していく「自治」の重要性を示している。(太文字はuco山口編集)
このコラムは、東洋経済オンラインの「こども食堂から一線を引く」が良い記事だったのでそれを参考に再構成したものです。「こども食堂から一線を引く」 《こども食堂》の名付け親が決意した背景 ボランティアでできる支援には限界がある