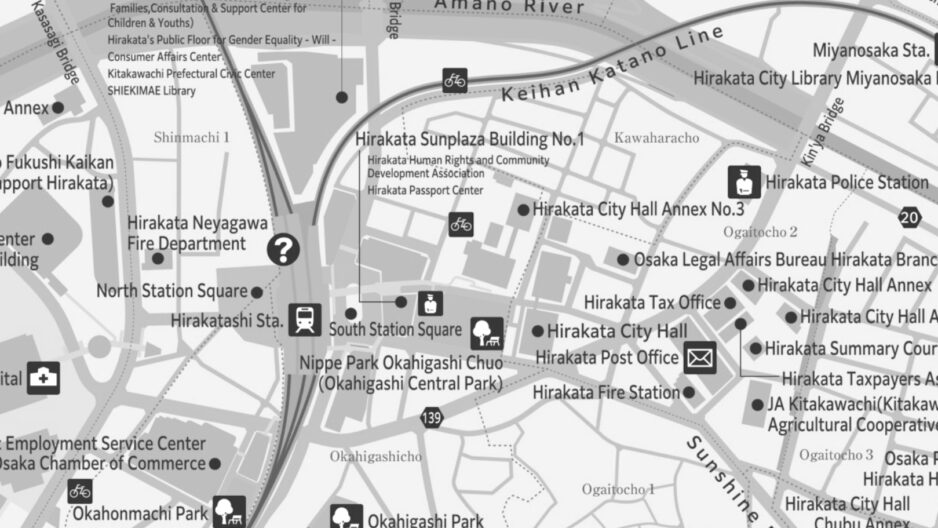 再開発問題
再開発問題 枚方リデザイン 第2回
駅前-市役所-旧市民会館を縫合する“連結型シビックコア”という提案枚方市駅周辺多言語マップより (Hirakata city station area multilingual map) | 枚方市ホームページ枚方市駅から市役所まで、歩いた...
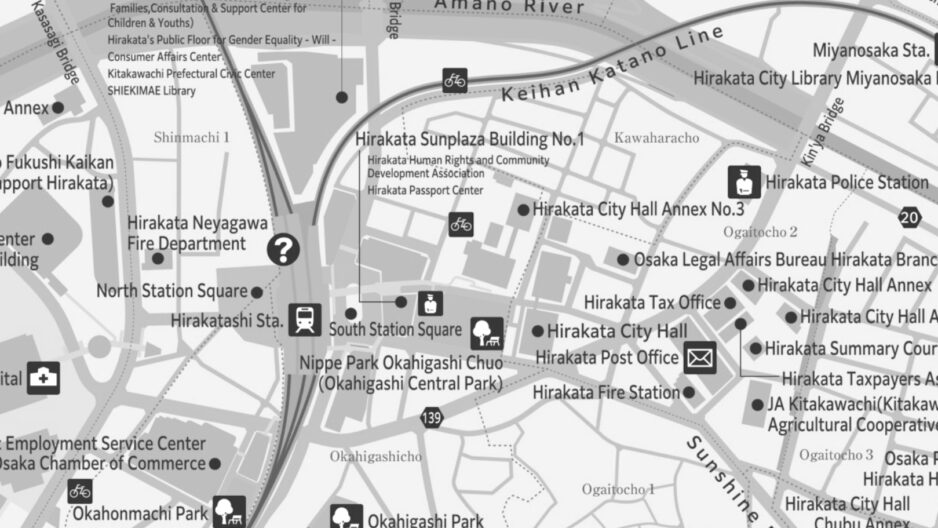 再開発問題
再開発問題  コラム
コラム  エネルギー地産化、地域化
エネルギー地産化、地域化  コラム
コラム  再開発問題
再開発問題  エネルギー地産化、地域化
エネルギー地産化、地域化  コラム
コラム  大阪市地方自治の現在地
大阪市地方自治の現在地  レポート
レポート  コラム
コラム