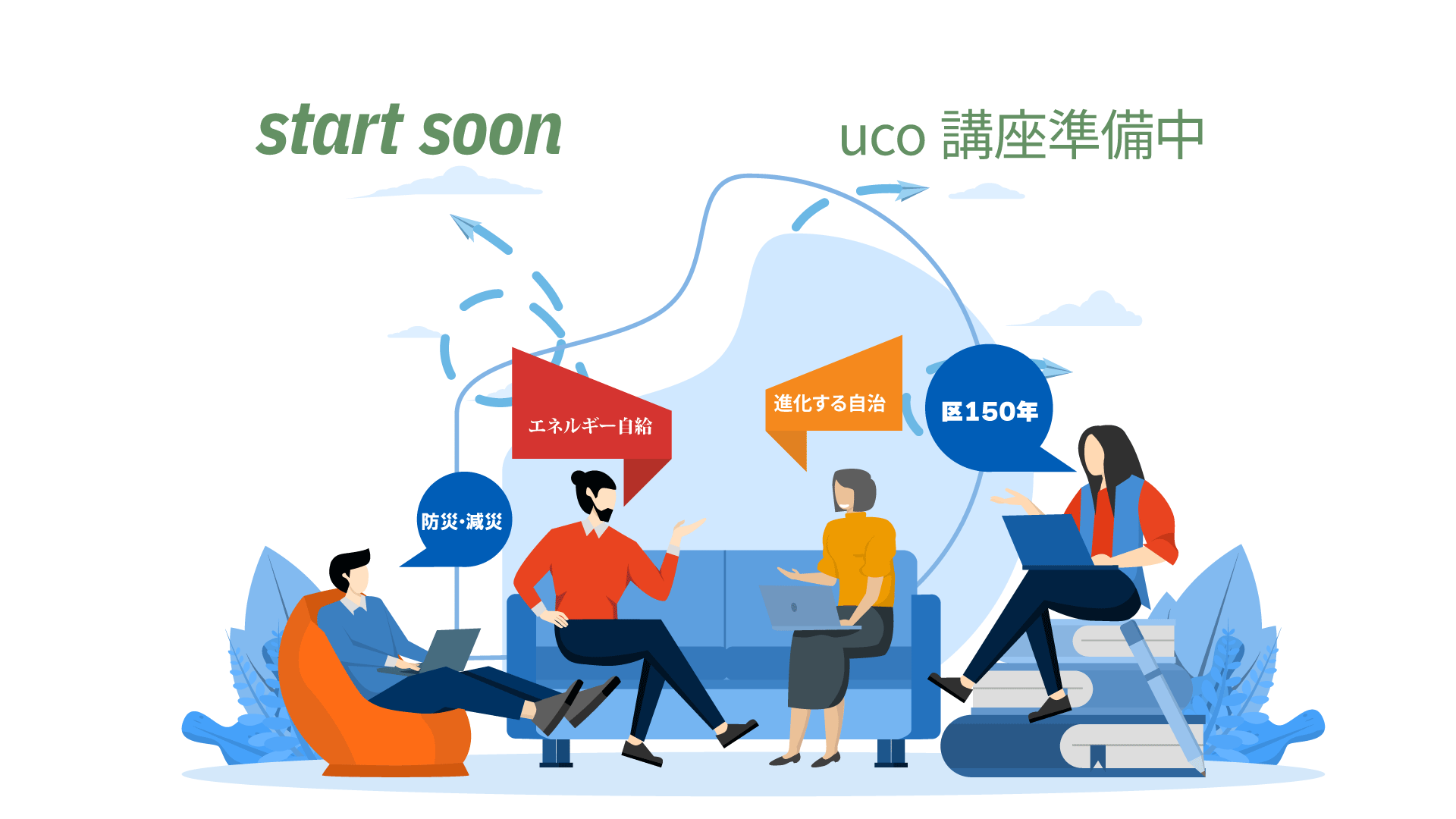ucoでは、「進化する自治を構想する」をテーマに、様々な視点から自治のあり方や市政への反映の手法などを探っていこうと考えています。
その一つとして、シリーズで講座を実施していきます。
今回は、「大阪の未来を構想する」行財政編パート1として、大阪市政のスタートから現在までの行財政を振り返り、現在の大阪市をかたちづくってきた特性と、これからの大阪市政は何を根底とするのかを探る「大阪市行財政の軌跡とその特質を考える」を全5回で実施いたします。
長く大阪市の行財政にも携わってきた木村収先生を講師にお迎えしてお送りします。
第1回は、大阪市発足明治、大正、昭和戦前期までの大阪市の行財政を振り返ります。明治維新後に始まる近代化の中で、経済復興、自然災害や疫病対策、各種インフラ整備などの都市整備の一方、税収不足の中、近代港の建設、産業の工業化を経て、大大阪と呼ばれるに至る、大阪市政と地方自治について学びます。
講座内容
はじめに
1 市政を特徴づける自然・社会・経済の特性
かつての市政を記録し書誌情報として残し続けた大阪市
→ 電子情報として垂れ流し、書誌情報化はしない都市( 市政だより・統計書etc.) ←現状 (P1)
① 水に弱い地形-河川、港として活用 (P2)
② 新田開発と埋立 (P3)
③ 面積・人口の変遷 (P4)、市域拡張 (P5)、六大都市人口の推移[1893 ~ 1918] (P6)
④ 都市・発展段階( クラッセンのモデル) (P7)
⑤ 大阪経済発展の沿革 (P8)
⑥ 疫病とのたたかい-コレラ・赤痢 (P9、P10) →コロナ
⑦大火 (P11)
⑧ 台風 (P17)
2 戦前期地方自治制度
⑴ 市制町村制の制定 (1888 年< 明治21>)
●三府の東京、京都、大阪の三市には「市制特例」( 府知事、書記官が市長、助役の職務を行い、
市参事会は知事、書記官および名誉職参事会員をもって組織 (P13)→1898 年<M31> 特例廃止
⑵ 府県制・郡制の実施 (1890 年<M23>) (P14)
●府県知事および郡長の所轄する国の行政区画であり、同時に地方公共団体の区域
●主要な補助機関も国の官吏で構成される等住民自治の要素は「極めて希薄」
⑶ 市制町村制は市政と町村制へ[1 つの法律から2 つに分離] (P15)
●市の執行機関は合議制の参事会から独任機関としての市長( 任期4 年) に改め、市参事会は副議決機関へ
⑷ 府県制の改正(1892 年<M25>) (P15)
●府県会に三府以外にも三部経済制を拡大(1892 年<M25>)
●府県が法人であることを明記(1899 年<M32>)
●府県にも条例規則の制定権(1929 年<S4>) ( 自治団体としての性格強化)
⑸ 郡制の廃止 (1921 年<T12>)、国の行政機関としての郡長制度廃止(1921 年<T12>)(P16)
⑹ 1930 年・31 年<S5・6>) から準戦時体制ないし戦時体制に入る→自治的風潮衰退
1940 年<S15> 頃から戦時体制色強化 (P16)
⑺ 1943 年<S18>) 改正により、府県も市町村も国の中央統制管理の下へ (P17)
●市町村会の議決事項は概括例示主義から制限列挙主義へ
●従来市町村会の選挙によって選出された市町村長を、市長については市会の推薦した者につき勅裁を経て
内務大臣が任命。町村長については町村会の選挙した者について知事の認可を要することに。
●東京市と東京都を合体して都長官が管轄する東京都制の実施。
●町内会、部落会を法制化しと町村長のもとへ。
⑻ 国の地方行政組織と旧地方自治制度 (P18)・旧地方自治制度の特色 (P19)
- 久世公堯『地方自治制度』による
3 大阪市-戦前期の制度と市政の展開
⑴ 大阪市をめぐる大都市制度のあゆみ (P20 ~ 22)
⑵ 市政のあゆみ( 大阪市政年表) (P24 ~ 29)
⑶ 歴代市長 (P30、31)
⑷ 学区 (P32)
●1889 年<M22>、市制特例実施を機として四区での小学校経営を全市一学区とする共通経済とすることに
改める。
●1890 年<M23>、地方学事規則・小学校令の改正で学区制度認められる。( 府知事の裁量で設け得る)
●市会意思に反し、1893 年<M26> 年度から実施(43 学区) → 1926 年<T15> まで34 年間続く。
(67 学区中、尋常小学区65 は廃止、任意学区2 は当面存続)
⑸ 戦前期市政五大事業( 本庄榮治郎論文) (P33 ~ 37)
① 上下水道、② 電気鉄道、③ 築港、④ 都市計画、⑤ 社会事業
⑹ 池上・関市政 (P38 ~ 45)
4 戦前期地方財政の特質
① 地方財政の歴史的性格 (P46)
② 明治地方制度と地方財政 (P47 ~ 49)
③ 大正デモクラシーと地方財政 (P50、51)
④ 恐慌と戦争期の地方財政 (P52、53)
- 佐藤進、高橋誠編『地方財政読本( 第2版)』による
5 戦前期大阪市財政の特質
① 財政 (P54)
② 市政 (P55)
③ 全国にさきがけた事業の例( 一部戦後を含む) (P56)
④ 五大事業の参考資料
(ⅰ) 水道 (P57)、(ⅱ) 下水道 (P58)、(ⅲ) 電気鉄道・交通 (P60)、(ⅳ) 御堂筋と受益者負担金 (P61)、
(ⅴ) 電燈事業 (P62)、(ⅵ) 都市計画事業 (P63)、(ⅶ) 港湾 (P64、65)、(ⅷ) 教育 (P66、67)
⑤ 普通経済の体系(1941 年<S16> 年度 (P68)
⑥ 大阪市普通経済・特別経済の年度別の状況( 明治・大正) (P69)
⑦ 明治・大正期大阪市財政歳出・歳入構成比推移 (P70)
⑧ 明治・大正期大阪市歳出総額( グラフによる推移) (P71)
⑨ 明治・大正期大阪市歳出の内訳割合( 図表) (P72)
⑩ 明治・大正期大阪市歳入の内訳割合( 図表) (P73)
⑪ 昭和戦前期大阪市の会計区分( 図表) (P74)
⑫ 明治・大正・昭和大阪市財政規模の推移( 図表) (P75)
⑬ 歳出・歳入決算推移詳細資料 (P76 ~ 82)
⑭ 市民の市税負担( 昭和元~ 20 年度<1926 ~ 1945>) (P83、84)
⑮ 市民の市税負担( 明治30 ~ 44 年度<1897 ~ 1911>) (P85)
⑯ 1940 年税制改正前後の大阪市税 (P86)
⑰ 戦前の地方税体系及び税収額( 全国) (P87 ~ 90)
この講座アーカイブを購入する
![「大阪市行財政の軌跡とその特質を考える[全5回]」第1回 戦前期の行財政-1989(明治22)~1945(昭和20)-](https://ucosaka.com/wp2025/wp-content/uploads/2025/05/osakacityhistory_01_1080.jpg)